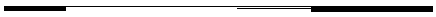
特撮映画のビジュアル技術は映画「ロード・オブ・ザ・リング」の成功で一つの頂点を迎えた。今後それらのノウハウが個々の映画に如何に生かされるかが楽しみである。静やかな文芸大作の中でひっそりと息づく自然なCGが「雲待ち」で何ヶ月も撮影が足止めされるという製作上の無駄を省き、監督はドラマ部分の演出により集中できる環境が得られるだろう。特撮の一つの頂点はそれが特撮だったことに気がつかせないことでもある。平成版「魔界転生」の「大名行列」がささやかにCGだったりするのは代替撮影としての特撮の面目躍如である。「フォレスト・ガンプ 一期一会」の頃から頻繁に使われていたさりげないCG。かつての東映時代劇のように延々と続く「大名行列」を撮影できない今の日本文化の貧困を埋めるには貴重で効果的なテクニックである。しかし芝居の書き割りや画面の寂しさの埋め草としてばかりの特撮ではなく、たまにはスカッと脳天気な「大特撮」を楽しみたいときもある。それを完全に見せ場として作られた活動大写真、スーパーヒーローの映画を無邪気に楽しみたい。
「スターウォーズ」や「未知との遭遇」が大きく改革したSF映画の世界。その特撮技術を生かしたスーパーヒーロー映画がハリウッドで量産され始めたのはクリストファー・リーブ主演の「スーパーマン」からである。その後、「フラッシュ・ゴードン」や「ロケッティア」、続々とアメコミヒーローが銀幕に勇姿を見せて今日に至っている。「スーパーマン」4部作が終了してからは、主役よりも常に敵役が話題になる「バットマン」、近くは「Xメン」「スパイダーマン」「ハルク」等、枚挙に暇がない。日本も2004年はアニメの実写リメイクブームが起こっている。しかし劇場映画というものは一つの映画としてその世界を完結させる必要があるので、シリーズを通じて活躍して認知されていくヒーロー物語を描くにはそもそも不向きなものではある。だからスーパーヒーロー映画は原作やテレビで既に「ご存じの」ヒーローでないと成立しにくい。劇場映画オリジナルのスーパーヒーローが果たしてどれほどいたろうか、全く記憶にない。映画がヒットして続編が出来、そしてシリーズ化されて初めて映画オリジナルのヒーローといえるだろうが、かつての映画黄金期ならばいざ知らず、現在は成立しがたい。「スーパージャイアンツ」や「月光仮面」が劇映画としてシリーズ化されたのは「テレビ」のない時代だったからであって、原作のないスーパーヒーロー映画は昨今全く成立していないようだ。前出の「マトリックス」のネオは確かにスーパーヒーロー的になってしまう場面もあるが、彼は変身ヒーローではないので、私がここで語ろうとしているスーパーヒーローの範疇には入らないのである。「電光超人グリッドマン」の世界に人間がダイブした話として捉えるのは強引かつマニアックなのでここでは言及しない。又、特撮を生かしたヒーローではあるが「ジェームズ・ボンド」や「インディ・ジョーンズ」「ララ・クロフト」たちは冒険アクションヒーローと捉えるべきなので、ここではスーパーヒーローとは考えないことにする。
七十年代に放映わずか七回で打ち切られたテレビ特撮のヒーローが映画で復活するというのは、スーパーヒーロー映画の成立として定石的設定なのである。人気の監督と脚本家と役者が結集して三十年前のヒーローが帰ってくる。そう、ヒーローは「帰ってきて」こそヒーローなのである。そして「ゼブラーマン」は「帰ってきたヒーロー」として作られて銀幕に登場した。話がややこしくなってしまうのだが、スタッフたちは実際に存在したテレビ特撮のヒーローを劇映画で復活させたのではなく、実は初めからオリジナルのヒーローを想像したのである。「放映わずか七回で打ち切られた」ので見た人が少ないため、カルトな作品になったという話自体が架空の話でしかない。なんとも凝った仕掛けを用意したものである。かつてそのようなテレビ番組が存在したかのような設定の映画なのである。中には「俺、昔見たことあるよ」と知ったかぶりをした人もいたかも知れない。かく言う私はころりと騙されて、ゼブラーマンは七十年代の無名のスーパーヒーローと信じていた。七十年代は奥が深いなぁと映画を見終わった後でも、すっかりその気でいた。事実、私は「電人ザボーガー」や「超神ビビューン」。「炎の超人メガロマン」等は全く見ていないという極普通の中高生だったのである。
テレビの特撮ヒーローが銀幕に帰ってきて成功する例は実はあまりない。「月光仮面」にしろ「エイトマン」にしろ「仮面の忍者 赤影」にしろ評価はさんざんだった。テレビ版を銀幕に復活させる第一義は原作ファンやテレビ版のファンを観客に当て込めるという安易な営業サイドのソロバンにある。だから日本のテレビ番組や映画には原作が漫画であることが異常に多い。安易な企画よりも製作現場の志が真にファンを納得させる作品を生み出す。劣悪な条件で踏ん張っている製作スタッフには頭が下がる思いがする。しかし、如何せん予算不足なのかスタッフが勘違いしていたせいなのか、この手の映画は原作ファンからは言うに及ばず、テレビ版のファンからも厳しい評価しか得られない作品がほとんどだった。一部の好事家が喜ぶ作品を作ってもダメなのである。大衆の支持を得て認知されなくてはスーパーヒーローとは言えないのだから。「ゼブラーマン」は幸いにも原作ファンやテレビ版ファンを恰も当て込んでいるように見えて、実は全くのオリジナル劇場映画であったという斬新さで、その存在自体がユニークかつ面白い映画だった。
哀川翔命のVシネマの人。ヒーロー大好き親父。彼らに騙された年端もいかない子ども。わかったような批判を口にしたいオタク青年。これら4種の手合い以外を映画館に引きずり込むような映画的魅力は確かに乏しい。さらに映画館を出るときに彼らを満足させるような点があるとしたなら前半の筋運びなのだが、後半は「これが見たかったんでしょ、おタククたち」みたいな展開になるので、「んーっ違うよね、これは。」と多分誰でも感じてしまうと思われる。ともあれスタートダッシュの心地よさは天下一品だが、後半、予算が続かなくなるに従って監督の愛も底を尽くようで、金だけで成立している援助交際みたいな味気なさが漂う。ゼブラーマンという映画の物語としての骨格はコスプレヒーローオタクの冴えない中年親父が真のスーパーヒーローに成長して地球を救えるのかにある。結果的に主人公である市川新市は超人ゼブラーマンに変身して宇宙人を撃退する。彼は真の超人ゼブラーマンになった。私はそれがどう表現されたかを問題にしたい。結論から言うとそれは描かれていなかったと思われる。映画は映画の中で完結しなくてはならない。映画は表現であって説明ではない。ゼブラーマンがゼブラーマンとなる説明は映画の中できちんと表現されていなくてはならない。それが甚だされていないのである。この映画は前半の三分の一程度までは異常に面白い。家庭崩壊中のダメ教師で、コスプレ趣味の小心な主人公を笑う視点が小気味よく実に面白い。ちなみに哀川翔を初めとする渡部篤郎、鈴木京香ら出演陣の演技は素晴らしく、文句の付けようがない。特に哀川翔の演技はチャーミングであり、芸域の広さを感じさせてくれた。こんなにも凛々しくセクシーな鈴木京香は初めて見ました。ゼブラーマンに素直に憧れている市川新市(哀川翔)の純な親父っぷりには大の大人が今更変身ヒーローなんて恥ずかしいという部分で実に楽しく共感できたし、Xファイルに対する防衛庁特殊機密調査部の及川(渡部篤郎)の反応もリアリティがあった。浅野可奈(鈴木京香)のお尻のアップが延々と続く演出も好もしい。演技陣は充実していたと思う。防衛庁特殊機密調査部の活躍やゼブラナースの登場の頃までは好調な物語も、進行につれて徐々に亀裂が生じていく。ストーリー的な展開そのものには新味なく、波乱もないオーソドックスさなので、これが監督の演出力不足や脚本家の技量不足でないとしたら、彼らのこの映画に対する愛や志が元々いいかげんなものだったということになるだろう。コスプレ親父をコミカルに笑うべき存在として描き、細かく笑いを取るのは常套手段であり、自分よりも深いゼブラーマンオタクの小学生を「浅野さん」と呼ぶ新市の風情は抱腹ものである。「やーばい。浅野さんに見せたくなった。」とゼブラーマンのコスプレのまま街に出てしまい、右往左往する姿は実に愉快である。しかしカニ男との対決から次第に観客は取り残されていく。つまり本筋に触れ始めると物語がぶれ始めるのだ。スタッフたちの情熱はコスプレ親父を笑うところで枯渇してしまったのか。本筋(この場合はヒーロー物の定石・・努力、友情、勝利みたいな要素)のある物語をスタッフはきちんと描く気持ちが中途半端だったのではないだろうか。
決壊の瞬間までの静かな亀裂は、ゼブラーマンとして初めての覚醒する瞬間から始まっている。しかし、どうして新市が超人になってしまったのか、説明が一切ない。悪人、カニ男と遭遇して、彼の中に眠っていたゼブラーマンの魂が覚醒したなんてのはよくあるケースなので、後で宇宙人や宇宙人の残した資料で明らかにされるだろうと思って見続けていると最後まで明らかにされない。謎の多い超人とは言え出自的な謎が全く解明されていない。話の筋から言うと地球に味方する宇宙人が新市を何故か見込んで超能力を授けたみたいなのだがはっきりしない。宇宙人が彼に託した「ANYTHING GOES」というメッセージもよくわからない。ウルトラマンがどうして空を飛ぶのかを知っている人はいないが、ハヤタに宇宙人が憑依している設定は誰でも知っている。新市がどうしてゼブラーマンの力を得たのかはゼブラーマンという話の肝なのに全く明らかにされていない。宇宙人から超能力を授けられたのなら授けられたでよいけれども、その点がどうにも表現されていない。
コスチュームの入った鞄を抱えて学校を抜け出すゼブラーマンとしての日常が描かれている箇所は微笑ましいものがあった。前半のコスプレ版ゼブラーマンは格闘だけで敵を倒しているので、「月光仮面」や「バットマン」みたいなものかもしれないが、新市が元々格闘技の達人であったとは思えないので、あれは超人ゼブラーマンの力だろう。その力の源について全く省いてよいものとは思わない。人類滅亡の予言に立ち向かうためにゼブラーマンが飛行特訓をするシーンが描かれる。ゼブラーマンは人間体の時の特訓が変身後に生かされるという「帰ってきたウルトラマン」的存在なのか?それもわからない。ゼブラーマンがゼブラーマンたるシステムは明らかにしておくべき事だったはずだ。
また新市自身が自分がゼブラーマンであり、横浜市八千代区の平和を守っていることをどう思っていたのかに関する描写が全くない。カニ男や放火男を明らかにゼブラーマンは退治している。彼らは宇宙人に憑依された人間だ。新市は街の悪人(人間)を殺害し続けていたのだが、そのことを新市がどう自覚していたのか描かれていない。殺人行為について市井の人間として躊躇いはなかったのだろうか。スクールバスに乗った子供たちが全員宇宙人に憑依されてしまい、暴れ出すシーンがあった。新市はその中に自分の息子がいることを知り、息子だけを攫って助けてしまう。残された子供たちは防衛庁特殊機密調査部の火炎放射器で全て生きながら焼却処分にされたはずだが、その場面が描かれていない。宇宙人退治は憑依された人間殺しでもあるのだが、その部分に関しての新市の葛藤を描かなくても良いものなのか。「スーパーヒーロー映画なんだから固いこと言うな。」ではスタッフの見識が疑われても仕方がない。以上のような演出からゼブラーマンの内面は全く伝わらない。彼が何のために戦っていたのかすらも伝わらない。
米軍機が運んでくる中性子爆弾に「中性子爆弾」と漢字で書いてあるというベタなセンスはいかがなものかとも思うが、そもそもCGのレベルが低すぎて笑えない。米軍と政府は宇宙人を抹殺するために八千代区の人間皆殺し計画を実行中だったのだから、宇宙人退治も問題だが、こっちの方も重大事である。ゼブラーマンの活躍を米軍が認めて作戦を中止するはずがないので、宇宙人を退治した後は爆弾処理だと思っていたら、あっさり回避。「中性子爆弾」のCG同様にリアリティのないこと夥しい。米軍の動きにリアリティを持たせたならば、次の攻撃目標は「過剰な戦力を備えた危険分子、ゼブラーマンも抹殺」になるはずだが、これは次回の講釈か。
グレービー号に乗って少年を救わんと疾駆するぼろぼろのゼブラーマンの姿は格好悪いがカッコイイ。涙が出そうになった。少年の祈りと乙女の涙(ちと鈴木京香は年齢制限に引っかかるが)に応えてヒーローが颯爽と登場するというのはスーパーヒーロー映画の最大の見せ場であり、カタルシスである。少年が宇宙人に捉えられていることをどうしてゼブラーマンが知ったのかという不可解などは、この見せ場の前には霞んでしまう。宇宙人との対決の中でゼブラーマンは本当の(真?)ゼブラーマンに変身する。これにも理由はないのだが「額のZが光って真ゼブラーマンに変身だ!」という規定通りのノリは軽いもので、新市の血と汗と涙の飛行特訓を無駄にしているみたいで哀しくもある。これ以降、飛べないはずのゼブラーマンが空を飛び、「シマウマ」が飛ぶとしたらあの格好しかないなと想像したとおりの展開に至るまで、実にチープなCGと物語が炸裂する。映画ファンやスーパーヒーローファンをなめてんじゃないのと疑いたくなるような、大いに脱力させられるクライマックスだった。もっと予算があればビジュアル的にはどうにかなったかも知れないが、センスのなさは救われない。特撮的にも主人公の感情的な盛り上がりに関しても絶体絶命の危機的状況を作る作劇状の工夫に置いてもダメだ。脚本の練り込みに関しても監督の演出に関しても特撮のアイディアや撮影にテクニックについてもチャレンジ精神が露も感じられない。
宇宙人の造形のカワイイ、チープさは確信犯なのだろうが、女子中高生を映画館に呼ぶ効果は期待できまい。そもそも「ゴケミドロ」でしょ、あの宇宙人は。スライム状に合体して巨大化するシーンも予想通りで驚きがない。格闘系だった等身大ヒーローを巨大宇宙人と戦わせるのはいかがなものか。いっそのこと宇宙人は最後まで実体化しない方が不気味さが出ただろう。「マックイーンの人喰いアメーバの恐怖」をハードに哲学的に再現してもよかった。真ゼブラーマンスーツはバットマンスーツを意識した作りのようだが、ディティールはともかくバランスがよくない。口の部分を露出した仮面ヒーローは日本では成功しがたい。「星雲仮面マシンマン」と「ライダーマン」くらいである。バットマンやデアデビル、ジャッジドレッドたちは露出しているがそもそも彫像のような無表情な顎割れ西洋人でないと生口仮面は似合わない。バットマンを見て違和感がないのにマシンマンやゼブラーマンを見て格好悪いと思うのは、そもそも西洋人の顔が我々にはマスクのように見えるからだろう。日本人には全身を使うよりも、目や口元で演技したがる役者が多いので生口の仮面は似合わない。生目が出ている圧巻は大魔神であり、およそ仮面ヒーローとして成立したのは赤影(初代)くらいであろう。(ただし赤影は忍者であるからか元々表情に乏しい役者であっても許されたのである。)生口の仮面ヒーローとしては現実には初代「タイガーマスク」がいる。そもそも「ゼブラーマン」の発想は「タイガーマスク」に登場した「グレートゼブラ」に違いない。そうでなくして「ゼブラ」がヒーローになるとは考えられない。
映画「ゼブラーマン」のキーワードは【ヒーロー】【家族】【夢見る力】ということらしいが、スーパー【ヒーロー】の映画としては上記のように破綻が多い。【家族】の問題に関しては新市がスーパーヒーローになったから家族の絆が復活するというのでは映画のテーマに悖る。父は父のままで絆を復活させなくては感動は生まれない。新市はゼブラーマンになった。地球を救った本当のヒーローになった。しかしコスプレが趣味の中年男であることをやめてしまったら、新市はアイデンティティを喪失してしまう。栗田寛一はルパン三世になったことでルパン三世の物真似名人ではなくなった。寛一はルパン以外の物真似も出来るが、新市にはゼブラーマンしかない。ゼブラーマンとして怪人を倒していた頃の彼がコスプレを楽しんでいたとは思えない。趣味が使命となってはもはや趣味ではない。彼はたった一つの趣味と楽しみを喪失してしまっていた。スーパーヒーローとなった彼が家族の尊敬を受けたとしても、それはゼブラーマンが尊敬されているのであって、父である新市が尊敬されているのではあるまい。変なたとえだが道楽親父が博打で勝てば失われた家族の絆が取り戻せるのか。それは違うだろう。
【夢見る力】とは何か。それは「浅野さん」や新市が持っていた「テレビの特撮ヒーロー」に憧れる心を持続する力である。車椅子の少年である「浅野さん」は夢見る力を持ち続けていた。だから自分の足で立ち上がることでゼブラーマンに勇気を与えることが出来たのである。ところが新市はカニ男を退治して以降、夢見る力を失ってしまっている。現実のゼブラーマンの力を得て、彼は夢を見る心を失ってしまった。その夢見る力は最後まで復活しない。この映画の監督や脚本家にスーパーヒーロー映画に対する志はあったのだろうか。この映画はヒーロー映画としてなんらかの風穴を開ければ成功したに違いない。手っ取り早く敵をまとめるために合体させたりしなければ、クライマックスでかなり踏ん張れた作品といえたかも知れない。中年男の自己再生の物語としてもっときっちりと描くべきだったのではないか。奇跡を起こすのは夢見る力だと叫んでみても、それを見失っている主人公に・・・・いや、そうでもないか。ゼブラーマンが空を飛んだ時、彼は夢見る力で、夢の翼を開き、敵を倒したのかもしれない。しかし、新市が【夢見る力】を取り戻したかどうかの白黒はまだついていない。
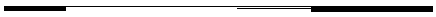
Copyright(C) 1980-2023 SUPER RANDOM Com. All rights reserved