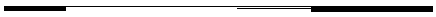
「世界のキタノ」の映画は本当に面白いのだろうか。外国で認めてもらったからと言うことを権威にする評論家や提灯持ちの輩はどこの世界でもいるわけで悲しくなる。洋画は見るけれども邦画は見ないと公言する自称映画ファンも多い。外国と日本では文化的土壌が違うから、資金のかけ方も違うわけで、同じ野球だろうとか言ったっておいそれと日本野球が大リーグで通用するはずがないのである。そんな中でイチローや松井、アニメと並んで北野武の映画は頑張っているようである。あのキタノブルーとかいう暗い画面は、暗いヨーロッパでは受けそうなので、その辺りがベネチア国際映画祭での受賞につながるのだろうか。私が見た北野武監督作品は数本なので、全貌を語ることは出来ないが、身銭を切って見た分の事は語ってみたい。
「その男、凶暴につき」。監督デビュー作である。この映画の沈んだ雰囲気は近作の「HANA−BI」にも通じる。そういえばどちらでもたけしは刑事であり、人殺しであり、心を閉ざして破滅していく。素朴な暴力が売りの北野映画の典型をいきなり作ってしまったわけだが、白竜との息詰まる駆け引き、へろへろになりなから街を激走するところが記憶に残る。真っ直ぐなカメラワークに素人っぽさがあった。リアルな暴力描写が素朴で非情に嫌らしい。爽やかな暴力アクションでなく、不愉快な暴力とカタストロフを描く姿勢というのは「Doolls」でも変わっていない。「3−4x10月」でも記憶に残るのは暴力のシーンである。「菊次郎の夏」はロードムービーで少年映画のような体裁を持っているが、夏休みの夢のような映画でハートウォーミングだった。未見だが「あの夏いちばん静かな海」はラブストーリーだそうなので、いずれは見てみたい。「HANA−BI」は転落していく元刑事と病魔に冒された妻の逃避行、「Doolls」は狂気の男女のロードムービーを縦糸としたラブバラット。こうして振り返ってみるとロードムービーが多い。何故だ。ロケが好きなのか。とはいえ、「Doolls」は日本はこんなに綺麗だったということを再確認してくれる。バブル期の企業の作っていた豪華なカレンダーみたいな映像だった。文楽や歌舞伎はとんとわからないのだが、「Doolls」は素人の実験映画みたいなところがあってワクワクした。ひたすら歩くという行為をしんどく見せるためには固定カメラワンカット長回しがいいのではないかというアプローチだったと思う。雪の中を二人が遠くに歩いていくロングショットなどはたぶん面倒だったからワンカットにしてしまったのだと思う。土手を転がり落ちるロングショットなども、あれはカットを割るのが面倒くさかったに違いない。とはいえ、総じて悲惨で切ない映画が多かった。自分はヒーローしか演じないくせに監督するととたんに暗い映画を撮りたがるのはクリント・イーストウッドや勝新太郎だが、北野武もそうらしい。
さて、ヨーロッパの映画祭でいくら賞を取っても日本でヒットするとは限らない。北野武監督作品が大入りしたという話はあまり聞かない。深作監督の「バトルロワイヤル」は少ししか出演していなかったが、あの映画は大ヒットしたのに。北野武も昨今の時代劇ブームに乗ってチャンバラを撮ってみようと思い立ったのは正解だったかも知れない。それも「座頭市」という大看板、勝新太郎一代の当たり役である。ここに目を付けたのは慧眼である。「座頭市」だなんていう勝新太郎以外ありえない時代劇ヒーローに挑戦というのは、無謀であって失敗して当たり前である。しかし、座頭市という日本映画の財産的なキャラクターが勝新太郎の死と共に封印されて良いものか。そう考えたときに、ドン・キホーテがいてくれないと、次の座頭市が生まれない。かの「007」はショーン・コネリーのイメージもさすがに5代目までくれば引きずっている観客はいないわけで、未だに「ショーン・コネリー」しかいないと思っている観客は初恋の人が忘れられずに狂気の世界の住人となっている松原智恵子(「Doolls」)みたいな人であろう。これが突破口となり、新たな座頭市伝説が始まるかも知れない。リスクを冒さない挑戦者はいないのだ。また、北野武の読みとしては今あげた「負ける意義」もあったかもしれないが、役者「ビートたけし」という強烈な個性のある配役で真正面から座頭市に挑戦というアグレッシブな意義もあったろう。初代のイメージが強烈に成功している場合、2代目はそれ以上にド派手に行かなくては、初代のイメージを拭えない。金髪に赤い仕込み杖という派手な衣装もその一端なのだろう。しかし時代劇のヒーローには爽やかな暴力が不可欠なのだが、リアルで不快な暴力を追求し続けてきた北野映画が方向転換できるのかは実は重大な問題でもある。
さて、先ずは外堀から眺めていくとどうか。田圃での農作業とか、大工仕事とか、村祭りとかをタップダンスのリズムでという音楽的な遊びをやっているがちと過剰なサービス。田圃での鍬の振り方などは無意味にしか見えない。きちんとした作業で音楽に乗るのならば意味もあるだろうが、あまりにも意味がない。自然音を音楽にするという発想は黒澤明的ではあるが、黒澤の場合は自然音だから許せるが、北野のそれは作為が多すぎる。夜間照明は適度な暗さで良かった。ただ室内がもっと暗くても良い。外に写る障子の明かりがフラットで明るすぎて興ざめがする。雨の降らし方もまずい。盥の中の落ち葉や農家の蝋燭立てが少し嫌みでだった。タップダンスの群舞は圧巻ではあるが、座頭市本人と絡んでいるわけでもない。解放された民衆のパワーの表現としてもそぐわない。「七人の侍」におけるラストの田楽シーンへのオマージュなのだろうか。
北野座頭市は強いのか。最大の関心事は殺陣である。目にもとまらぬ早業で斬って斬って斬りまくるのか。ここが私にとっての大きな関心事だったが。正直に言うともっと斬って欲しかった。少なくとも前作の勝新太郎監督の「座頭市」のラストバトルに匹敵するくらいは斬って欲しかったのだが、勝の重戦車のような力強さは感じられなかった。勝座頭市は仕込み杖らしいカミソリのような鋭さと豪剣でぶったぎるという感じが同居するのだが、北野の仕込み杖はカミソリでしかなかった。リアルという点で言うと北野座頭市のカミソリのような怖さもなかなかよい。CGの血糊は豪快に吹きまくっていた。刀の柄を斬ったり、石灯籠を斬ったりという豪剣ぶりも見せるのだが、乱戦の時のパワフルさがあと一歩欲しかった。受け太刀をせずに相手を次々と斬り裂くというのは、くるくると刀を振り回していれば相手が勝手に倒れてくれると考えれば、「あずみ」と同じになってしまう。しかし上戸あずみが全身で刀を振るっていたのに比較して、北野座頭市は手だけで斬っていた。まっ座頭市は居合いであるので、敵を斬り倒すとすぐにニュートラルな状態に戻ってしまう。それはそれでよいのだろうが、どうにも決まらない。残心がない。殺陣的にはこれでもいいのかもしれないが、この映画はそもそもアクション映画にはなっていないのである。殺陣であり、剣劇はともかくも、剣劇アクションになっていない。アクションの至らなさをCGやカットバック、スローモーションや大げさな効果音で補っていると考えれば、一応はハリウッドスタイルではある。外国人にはそれでもいいのかもしれない。竹槍を立てに割いたり、障子越しに斬ったりするのは勝座頭市へのオマージュだろう。竹槍を裂くのはCGを使ったので抜群のスピード感だったが、障子越しの斬撃はあそこだけテンポが落ちていたのは何故だろう。目にもとまらぬ高速殺陣は無敵の強さである。全く危険な目に遭わずに敵を撃破していく強さというのはスチーブン・セガールみたいでもある。
本来、さらに重要なはずの座頭市のキャラ立ちはどうだったか。これも大きな「?」を入れたいところである。行きずりの仇持ちの姉弟に肩入れするのはけっこうだが、その肩入れする理由が見あたらない。不幸な境遇に同情するのもよいが、心を寄せていく過程が感じられない。座頭市は賭場を破るわけだが、なんで賭場を破って殺戮するのかよくわからない。ヤクザだから殺戮しても良いというのはおかしな話である。あれではただの殺人狂である。勝座頭市はそれ自体にユーモアや滑稽味、ペーソスがあったが北野座頭市にはそれがない。たけし軍団がさかんにコントを繰り広げるのだが、ストーリーとはかみ合っていない。北野座頭市が積極的に土地のヤクザを退治する動機付けが弱い。北野座頭市がクール&ドライなのかというとそうでもない。意味不明のキャラクターとなっている。無頼な殺人狂なのか、それとも世直し旅をしている正義の味方なのか?
ストーリーの進ませ方に必然性やドラマ的盛り上がりがないので、コントが箸休めになっていないのだ。細切れのコントやショートエピソードがバラバラに詰まっているだけのようだ。托鉢僧の集団が座頭市の居候先を襲うシーンでは、托鉢僧の集団の存在そのものがおかしかった。忍者ではあるまいし、托鉢僧の集団というのは記号的すぎる。あの一行は盗賊の首領の親衛隊らしいのだが、浅野用心棒を差し置いて、どうして親衛隊が座頭市を斬りに行ったのかわからない。更には盗賊の親衛隊が忍者だったりとめちゃくちゃである。外国人が好む、ニンジャムービーとかサムライムービーとかいうものはこんなものなのか。外国の日本レストランのような違和感がある。盗賊のお頭は誰なのかというのもミステリーの一つだが、功成り名を遂げ、勝手し放題で、この世に何の未練もないような大盗賊の晩年にしては、ちと世を忍びすぎているではないかとも思われる。北野座頭市の金髪に関しては納得のいく説明があるのだが、他の登場人物たちは金髪に関しては何の反応も示さない。白髪頭だと思っていたのだろうか。
日本人が相手にしないから、世界を相手に映画を撮るのだというのも悪くはない。しかし、時代劇はきちんとたエンターテイメントになっていてほしい。たとえば敵側を演じた俳優陣にあまりにも「いつもの顔ぶれ」を揃えてしまって新味がない。新味がないというとは。それだけエンターテイメントに相応しい布陣だったと言うべきなのだが、この時代劇はそのエンターテイメントを誤解しているとしか思えない。北野流に人間を描いてしまうと暗く切ない人間たちが登場してしまい、娯楽からは遠ざかってしまう。だから人間を描かなかったのかも知れないが、それにしては薄っぺらいものになってしまった。北野監督はビートたけしに「座頭市」を演じさせるべきだったし、少なくとも自分が監督するべきではなかったようだ。黒田義之や三隅研二とは言わないまでも、せめて深作欣二や工藤栄一がメガホンを握っていれば時代劇らしいものになったかもしれない。惜しむらくは時代劇アクションを撮れる監督はもう日本にいないということなのか。無論、一番良かったのは梅を演じた大楠道代である。出演者の中で最も役者らしい演技を示していた。
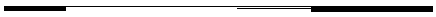
Copyright(C) 1980-2023 SUPER RANDOM Com. All rights reserved