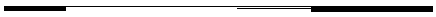
真田広之に期待する思いは何年も前から持っていたが、2002年11月2日公開の「たそがれ清兵衛」は実によかった。日本映画に新しい名作が誕生したというフレーズは聞き飽きたが、久しぶりにそのフレーズを堂々と当てはめてみたい映画だった。
ずっと髀肉の嘆をかこっていた真田広之がついに代表作に巡りあえた。「たそがれ清兵衛」。彼が動けるうちにやっと手にしたアクション時代劇であり、日本映画界の至宝といっていい。元々山田洋次監督の映像美には注目していた。誰も大騒ぎはしなかったけれども、「男はつらいよ」のロケシーンの巧妙な撮影、特に照明の設計は素晴らしいものがあった。その感覚が十分に時代劇の中で生かされれば凄い作品が出来るだろうと密かに私は期待していた。期待に違わず冒頭の清兵衛の妻の葬儀のシーンがはじまったとたんに「これは凄い。」と感じさせた。こんなにナチュラルな照明で映画を撮ってくれる監督は今時いない。そして清兵衛の住居の周りの風景。これが日本だと涙を流して訴えたい風景がそこにあった。食事のシーン一つをとってもリアルな描写が続く。それをしっとりと岸恵子の語りが運ぶ。
清兵衛と娘の「なんのために学問をするのか」という問答。これは寅次郎と満男の会話そのままだ。藩の上役たちの描写はキャスティングを含めて釣りバカ日誌そのものである。今、日本映画界最高のバイプレーヤーを上げよと言われれば誰も否やは言うまい、大杉漣、小林稔侍、吹越満。大杉漣が見事な太刀さばきを見せてくれる。小林稔侍はまるで社長シリーズの小林桂樹そのもの。「ホワイト・アウト」での誠実ぶりが記憶に残る(個人的にはシュシュトリアンのフライドチキン男に尽きるのだが)吹越満。無責任シリーズの人見明の再来かと思われる円熟味を増した赤塚真人の飄逸ぶり。本物にしか見えない神戸浩。なんで、あの場にいたのか訳がわからない尾美としのりに至るまで、実に隙がない布陣(浮いていたのはCGの蝿だけ)。そして、こんな人間を役者として使える懐の深さが日本映画界にあったのかと実感させてくれた強烈な田中泯。ちょっとメイクと演技に凝りすぎたが、全盛期の山崎努を彷彿とさせる容貌と佇まい。彼をあれだけの剣客に仕立て上げた殺陣スタッフの演出力。殺陣の経験がない宮口精二に世界一の侍を演じさせた黒澤組の演出力に匹敵する。
真田広之という役者はそもそもあのノーブルな狐顔が禍して役者としての幅が少なかった。真面目なヒーロー(「僕らはみんな生きている」「伊賀忍法帳」)。又はただの無味乾燥な二枚目(「翔んだカップル」「道頓堀川」)でしかない。その二枚目ぶりをギャグ(「どっちにするの」「伊賀野カバ丸」)にしたり、きつめに走らせると悪役(「必殺4」「陰陽師」)になる。しかし、今回は非常に人間味のあるキャラクターを真田広之が演じている。清兵衛のようなキャラが時代劇になかったわけではない、ただこのようなキャラを真田広之が演じられるようになったことが収穫だった。宮沢りえの時代劇姿と言えば「四十七人の刺客」を彷彿とさせるが、年齢を重ねることが時代劇という空間の中ではこんなにも輝きを増すことにつながるのかと思わせる。抜群の存在感が丁寧な演出の中に生きている。この味はぶっきらぼうな北野武の演出では出せないところである。要するに真田と宮沢の好演が光っていたのであるが、これらはすべて脇を固める演技陣の確かな造形と製作スタッフの充実があってこそなのである。主役はもとよりエキストラに至るまでの……それこそ、清兵衛の隣家の農婦の佇まい一つとっても、実にリアルに真田たちの演技を支えている。タイトルロールに流れる製作スタッフの一人一人の情熱の賜である。
娘二人と痴呆が進んでいる老母との貧乏生活にあえぐ清兵衛に上意討ちの藩命が下る。藩命とはサラリーマンにとっては社命だろう。社命とあらば牛肉のラベルの貼り替えや原子炉のひび割れ隠しだってやってしまうのが、日本のサラリーマンである。彼らと清兵衛を同一にしては武士道が泣くだろうが、似たようなものか。幼なじみの朋江(宮沢りえ)との縁談話を自分の貧乏を理由に断る清兵衛の愛の誠実さ。練りに練られた脚本。決戦の地に赴く直前、清兵衛の髪を梳く朋江と無言の清兵衛の間に静かに残酷に流れる切ない時間。互いに愛し合っているのは十分に分かり合っているはずなのに言葉が出ない。すべての身支度が済んだ後、堰を切ったように清兵衛は朋江に告白する。「もし、生きて帰ってきたならば、私の妻になって欲しい。」こういうタイプの中年男は土壇場にならないと愛の告白なんて出来っこないだろうと思わせる説得力溢れている。しかし、朋江はすでに五日前に別な縁談を受けてしまっていた。打ちのめされる清兵衛。「でも、私は断ります。実家から縁を切られてもかまいません。あなたの帰りをここで待ちます。私のためにどうぞご無事で。」と答える朋江の眼差しを背に清兵衛は決戦の地へ向かうのであった……という展開を期待したのに、朋江の返事は「私はあなたの帰りをここで待つことは出来ませんが、御武運をお祈りします。」地面の底が抜けるような衝撃を清兵衛だけでなく観客までも受ける。これじゃあ、決闘に勝てっこないよ。せいぜい相討ち。絶望的な清兵衛と観客の思いとは裏腹のピーカンの昼下がり……、静と動が極まる死闘が始まる。この一作で山田洋次監督は日本映画界に巣食っていた黒澤明監督の亡霊を断ち切った。世界一の侍映画は「七人の侍」でもなければ「用心棒」でもない。「たそがれ清兵衛」である。
清兵衛が自分の家に戻るシーンに涙が出た。彼は何事もなかったかのように黄昏時に満身創痍の体を引きずって帰ってくる。いつもと同じように家族のために、今日という日を立派に過ごして自宅にたどり着こうとする。日本映画を見て映画館で涙したのは、黒澤明の「生きる」以来、19年と7ヶ月ぶりのことだった。さわやかで感動的な涙だった。これは生まれて初めての経験だった。よかった、よかった。よい映画を見た。こんなによい映画を見ることができて幸せだった。心地よい満足感に包まれて映画館を後にした。
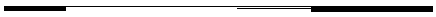
Copyright(C) 1980-2023 SUPER RANDOM Com. All rights reserved