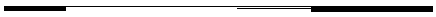

不思議な映画だった。サルでもわかる青春ジャズ映画である。片田舎の女子高生たちがふとしたことからジャズバンドを組むことになり、やがてその魅力の虜となって晴れ舞台を踏むという物語である。前作「ウォーターボーイズ」では男子高校生のシンクロという意表をついた素材を発掘した矢口史靖監督が、今回は女子高生にジャズという取り合わせで挑んでいる。男子とシンクロとにしろ、女子とジャズバンドとにしろ、どちらもコロンブスの卵かもしれないが、監督やスタッフの目の付け所や、それを作品にまで仕上げるエネルギーは素晴らしい。男子のシンクロが成功したのだから、2匹目の泥鰌を狙うというのはわかりやすい製作サイドの戦略であるので、スポンサー集めはしやすかったに違いない。
前作にしろ、本作品にしろ、小学生に見せたい。折しも、少子化は年金問題だけではなく、子供たちのサークル活動、部活動に深刻な影を投げかけている。野球チームが作れない。サッカーチームが作れない。運動会の選手すら揃わない。最近の小学校の運動会の演目は半分が父兄参加競技である。子供たちだけでは間が持たないからのようだ。離婚率も高くて父兄といっても母とお婆ちゃんばかりが目立つ運動会もあったりするので、親子競技の存在は子供たちに疎外感を生ませているのではないかと余計な心配をしてみたくなる。運動会は運動会であるから子供を運動という物差しだけでさらしものにするというイベントになりがちだが、運動以外の部門に打ち込む子供にも大舞台が用意されてもいいはずだ。市民体育館の片隅でひっそりと絵が貼られているというのは、あまりにも淋しい成果である。子供の趣味や部活動というものは大切に評価してやるべきだ。
高校生にもなると部活動で活発なのは一部の高校の一部の部活ばかり。大概は部員不足であえいでいるか、廃部。高校総体(インターハイ)に相当する高文祭という行事は知名度、認知度ともに低く、文化系高校生は日陰の存在だと言ってよい。根性のない文化部の衰退は著しい。その文化部の中でも唯一体育会的なノリを持っているのが吹奏楽部であるが、彼らの本来の活動である定期演奏会に足を運ぶのは親と幼馴染みくらいしかいない。高校の吹奏楽部は高校野球の応援演奏の時が最も注目を浴びる活躍の場である。やはり日陰の存在なのかも知れない。
ロックバンドは未だに「ロック=不良」の図式が前面に出てしまい、大人受けは良くない。「バイク=暴走族」といった世間の認識はだいぶ緩くなったのだが、「ロック=不良」というのはなかなか切り離すことが難しい。陣内孝則監督の映画「ロッカーズ」の面々は確かに不良度は高い。しかし、要するにまともに仕事に就いていないで、ロックバンドで名をあげようなんて若者は「不良」にしか見えない。その不良度が十分に魅力的であるのは、誰もが憧れる自由はすなわちアウトローでないと手に入らないからである。何より不良は少女の憧れである。彼らは非行少年ではなく、誇り高き不良少年を気取るものなのである。大林宣彦監督の「青春デンデケデケデケ」は普通の少年がエレキバンドにのめり込んでいく、清く正しい青春映画で、不良度は0。寺内タケシも泣いて喜ぶ文部省特選タイプの映画だった。

吹奏楽部とロックバンドの隙間的な立ち位置で本邦初の女子高生ジャズ映画「スウィングカールズ」が誕生した。吹奏楽部のオチこぼれが声をかけ、ロックバンドの残党が練習場所を求めて推参。そこに全くの素人女子高生たちが絡んできて、ドラマが始まる。食中毒を起こして演奏が出来なくなった吹奏楽部の代わりに、高校野球の応援演奏をする目的で急遽結成された「スウィングガールズ」だったが、吹奏楽部が復帰してくればお払い箱。人前で演奏することなくジャズバンドは解散となる。しかし、ジャズの魅力にとりつかれた主人公たちが細々と活動を再開し、師を得て次第に腕を上げ、仲間たちが再結集して……という青春サクセスストーリーが流れ出すという超前向きな映画である。
「ウォーターボーイズ」は自分たちの過ちのための借金返済が原動力。「スウィングガールズ」もそもそも吹奏楽部の集団食中毒事件を引き起こしたのは、無責任な主人公たちの過ちによるものだったので、実に共通項が多い。「スウィングカールズ」の場合は夏休みの補習をさぼりたいという下心もあって、吹奏楽部の代わりにジャズバンドを結成に至ったので、「ウォーターボーイズ」よりも性は悪い。飽きっぽくて無責任な女子高生気質が観客の抱く不快感を実に軽やかに無邪気にスィングして中和し、浄化してしまう。
ラストに発表会が用意されているのも「ウォーターボーイズ」と同じ構成である。晴れ舞台までがアクシデント続きでスリリングなのも相似。クライマックスが名演技、名演奏になりすぎているとしても野暮は言いっこなし。シンクロとジャズ、どちらも素人がきちんとしたコーチも受けず、短期間であれだけ上達し、大観衆を前にあれだけ凝った演技や演奏が出来るはずがないと憤るのは愚の骨頂である。二つの映画はクライマックスを純粋に楽しむべきなのである。「いかん、いかん。そんな馬鹿な。」という苦情は夢のない専門家にまかせておけばよい。二つの映画とも映画が終了したとたんにアンコールの拍手がおきても可笑しくない清涼感に溢れているではないか。

「カミカゼ・ガールズ(下妻物語)」の次は「スウィングカールズ」。邦画は女子高生パワーが豊作の2004年となったようだ。不良度の高い「カミカゼ・ガールズ」に比べると「スウィングガールズ」は不良度はかなり低くく、恋愛度も低い。リサイクルセンターのヤンキー兄弟もあっさりエレキを捨ててフォークデュオに走り、切ない恋心を叫ぶという軟弱ぶりだ。「スィングガールズ」たちの派手グループ (無自覚ヤンキー娘たち)は至極素直な者たちでせっかくバイトして買ったブランド品を売り払って新品の楽器を買ってしまったりと不良度は低く、非行度は0だ。タバコどころか飲酒もパチンコも改造バイクも一切無縁の無菌映画が「スウィングガールズ」の世界だったりする。「ウォーターボーイズ」は男同士の純愛が飛び出したりするが、「スウィングガールズ」には不純交遊どころか純愛劇の要素すらない。「カミカゼ・ガールズ」のヤンキー娘は恋愛に縛られていたが、「スウィングガールズ」は一人の失恋劇を描いたものの、大筋には全く関わってこない。恋愛から全く解放された女子高生たちは自由でパワフルである。恋愛と女子をセットにしなくては作劇できないと言う考えは実はステレオタイプな考えだったということだ。男子の行動原理の根本には「女の子にモてたい」という本能的欲求があるものだが、女子の行動原理の根本には「男の子にモてたい」という本能的欲求はないらしい。青春映画を作る場合には恋愛の要素は避けて通れないところなのだが、男子を主役とした場合は恋愛成就よりも「友情」「努力」「勝利」をドラマの中心におきたがる傾向がある。恋愛成就の目的は誰かが折れてこそ成立する。折れない強い女子を主役にしてしまうと恋愛劇の要素は二次的なものとなり、作劇上不要になるのだろう。
この映画は傑作ではあるが、空虚さがつきまとう不思議な映画である。それは主人公に余りにも魅力がないからである。主役を演じた上野樹里はキュートな若手女優ではある。しかし、彼女の演じた鈴木友子というキャラクターには全く魅力がない。彼女の演技に問題があるのではなく、鈴木友子というキャラクターに問題があるらしい。授業をきちんと受けていないから夏休みに補習を受けるはめになる。自分たちの野放図さが43人もの集団食中毒事件を引き起こしたことについての反省が全くない。そもそもジャズバンドを結成したのは吹奏楽部への贖罪からではなく、自分たちの過ちを隠蔽するためでしかない。届けるべき弁当を食べてしまったり、線路上にぶちまけた弁当の中味をそのまま箱に詰めたり、腐っているかもしれない弁当を他人に食べさせてしまういい加減さ。最後の演奏会参加までをスリリングな展開にしてしまったのも鈴木友子の無自覚な不注意からである。しかも、その重大な過失を大会当日の朝になっても口に出すことが出来ない。鈴木友子は普通の女子高生であって、飽きっぽくて無責任で自分勝手で何も考えていないドジである。そんな子が主人公になることは勿論かまわない。この映画における彼女の最大のセールスポイントはいち早くジャズに目覚め、前向きにジャズにのめり込んでいくところに尽きるからだ。しかし、肝心のジャズの魅力の虜になって……というジャズへの目覚めがきちんと演出されていない。「いぐね。いぐね。」だけで済ませてしまってよいものなのか。しかもそれによって彼女に何か変化はあったのか。……ない。ここにこの映画の命取りとも言うべき重大な欠点がある。

魅力のある個性的な人物が全く創造されていないのも弱点である。いかにもジャズ楽器らしいサックスを主人公。結成の中心人物である男子がピアノ弾き兼バンドマスター。大食漢にはドラムを与え、目立つトランペットには派手グループのリーダーを配置。引っ込み思案タイプにはメガネをかけさせ、楽器自体がアクティブなトロンボーンを持たせる。不良チックなロックバンドから流れてきたギタリストをショートヘアに、ベーシストをロングヘアにしてわかりやすくアピール。「スウィングガールズ」中、一番の常識人がこの二人だったりするのも面白いのだが、ロックンローラーたる彼女たちのジャズに対するスタンスは本来距離があるはずで、取り合わせの妙の域を脱してはいない。つまりこの配役は役割重視の戦隊ヒーロー的な色分けがあるだけだ。この映画を無邪気に歓迎している人に戦隊ヒーロー番組を笑う資格はない。
創作された人間の個性には幅や深みが滅多に生じるものではない。まして二時間完結型の劇映画では尚更である。主要登場人物の強烈な魅力を俳優がベストな演技で演じ切るというのは難しい。三遊亭園生の人情話の凄みはすべての登場人物をその端役に至るまで名人である園生が演じ切ってしまうことによって生まれるそうだ。集団劇において、すべての登場人物にアカデミー賞級の役者を揃えるのは無理だし、主役が「女子高生」では尚更である。芝居巧者だけを並べ立てたところで、アンサンブルとしてウェルメイドに仕上がるかは疑問である。一本の映画で表現できる個性豊かな登場人物の数は限られている。脇はその引き立て役に回らざるえない。だから、その映画の顔となる魅力ある主役キャラを創造して、俳優がそれをきちっと演じなければ、映画は成立しない。
「スウィングガールズ」の弱点は前述したようにキャラクターの、特に主人公に魅力がないということに尽きる。トランペット吹きやドラマーやトロンボーン吹きの子たちの方がまだしっかりとした属性やミニドラマを与えられている。(一番得な役柄を引き当てたのはトロンボーン吹きの関口香織を演じた本仮屋ユイカである。……ちなみに木下あゆ美と同じ事務所である。)つまり、主役の個性だけが妙に空洞化しているという奇態な映画なのである。つまり、鈴木友子には「この娘は主人公なのだ。」という扱いはされているが、それを説得させるだけの深みや魅力が与えられてはいない。鈴木友子は主人公なんですよとポスターの中央でいくら飛び跳ねていても、彼女には主人公として物語を引っ張っていく「力」が与えられているわけではない。
しかし、登場人物の造形が元々チープであっても、生身の肉体を持つ俳優がそれを演じると、俳優自身の息吹によって架空の人格に生命が吹き込まれる。そこに人間が描かれ、人格が一人歩きし始めるものだ。観客は映画館の座席に座りながら、コンサート会場の座席に座っているような錯覚を覚え、危なっかしい「スウィングガールズ」の演奏をはらはらしながら見守ることになる。そしてスウィングする。ここに劇場映画をスクリーンで鑑賞する醍醐味がある。観客は「スウィングガールズ」の誕生から発表会までを追っかけてきた熱烈なファンの役を演じることができる。観客もエキストラの一員となるのだ。劇映画も観客がいてこそ初めて成立する。その観客を映画の世界そのものに積極的に取り込んでしまうのが「スウィングガールズ」の仕掛けなのである。この効果はコンサートホールと映画館という状況の相似から「ウォーターボーイズ」のそれよりも数段大きい。

竹中直人は前作に引き続く登板。最近やたらとあちこちの映画で見かけるが、器用な役者ではないのだから、いつもの竹中直人でしかない。今回はマドンナ・白石美帆に一途な恋心を抱く独身中年男性という役作りのいらないような役で、サプライズがなさすぎる。その点、白石美帆はのびやかに田舎の美人音楽教師を演じていて爽やかだ。笑顔が往年の宮崎美子を彷彿とさせるが、きれいなバラには毒がある(?)タイプの女性をかなり素直に演じている。

映画にも二種類がある。面白い映画と面白くない映画だ。この映画は面白い。主役が空洞化しても、アンサンブルでそれを補っている。深刻なドラマ性を一切排してしまったのも潔い処理だ。引きずる過去も未来への夢も描かず、ただ軽やかにスウィングする現在を描く。こういう刹那的な感動を掬い上げた映画があってよい。この映画に主人公はなくてもよかったのだ。この映画は「スウィングガール」たちを描いた物語なのだから。
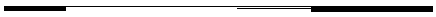
Copyright(C) 1980-2023 SUPER RANDOM Com. All rights reserved