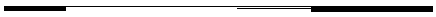
「下妻物語」はスマッシュヒットする映画に違いない。茨城県下妻市という地方都市を舞台にしたロリータファッション命の変な娘とヤンキー娘の友情物語である。そもそも日本映画なのだから低予算に決まっている。ゴジラ映画史上最高の製作費が二十億円だそうだから、「下妻物語」はいったいいくらかかっているのだろうか。とにかく十分に採算が取れる出来映えである。とはいえ映画館で盛んに変な予告編が流れていたが取り立てて見たいとも思わなかった。主演が深田恭子と土屋アンナと聞いただけて映画館に行こうという気は全く起こらなかった。本来ならば「キューティハニー」を観て、2004年邦画史上最強打線、二番手は内野安打でしぶとく出塁か・・なんてニンマリしていたはずなのに、どうして隣の劇場に入ってしまったのだろう。こういうのを運命の出会いというべきなのか、とかく期待値ゼロの映画だった。ところが得てしてこういう時に妙な傑作に出会うもので、この映画はたいそうよい。立派な映画になっていた。「CASSHERN」の監督は反省して勉強してほしい。ローカルな青春映画というのは昨今流行のようなのだが、かつての大林宣彦映画の「尾道」物は確実に尾道の街に息づくような生活感があってしっとりとした映像だった。こちらは乾いているが陣内孝則監督の「ロッカーズ」同様に元気があって疾走するタイプの若者映画で実よろしい。三遊間を破る強烈な当たりといったところである。
茨城フィルムコミッションが今回もあちこちで協力したものと思われる。東京から近い、土地と自然がある、昨今何かと茨城でロケをする映画やドラマ、バラエティは多い。多いことはよいことなのかというと微妙なところでもある。茨城県という土地に土着した映像作品では全くないはずの「ゼブラーマン」や「仮面ライダー555」なども、実はかなり茨城県でロケしているのだが、画面ではそれがわからない。横浜市や東京が舞台という設定なのだから背景が茨城ではまずいわけである。だからこれらはご当地映画というわけではないので地方ロケーションと言うよりも茨城県自体をオープンセットとして使っているようなものである。石井竜也監督の「河童」では昭和二十年代の茨城県が舞台で、子役たちに茨城弁を喋らせて地方色を出そうとしていた。小平裕監督の「タイガースメモリアルクラブバンド ぼくと、ぼくらの夏」は茨城県全域にわたってロケしていたし、柳町光男監督の「さらば愛しき大地」は鹿島が舞台である。安田公義監督の「新座頭市物語・笠間の火祭り」は座頭市のふるさとを舞台にしているとはいえ茨城でロケはしていまい、北野武監督の「座頭市」の方が茨城県でロケした場面は多い。とはいえ茨城県という何もないような田舎を舞台にしっかりと土着した映画も見てみたい。
さて地方ロケの命というのはその地方の空気感覚であると思われる。名所旧跡や駅弁が出てくればよいわけではない。土曜ワイド劇場のアリバイじゃないんだから、温泉と郷土料理さえ出せばというものでもない。観客をそこにトリップさせてくれるような小宇宙空間をそこに築けるかにある。これは大切なことであって、この空気感がないと映画はスタジオドラマと化してしまう。たとえば空気のないはずの宇宙を舞台にした本格SFを支えるのも空気感なのである。「スターウォーズ」は徹底的に地球の砂漠のような星や地球の密林のような密林の星を舞台にしてしまうことで濃厚な空気感と皮膚感覚を出した。こういった描写がないと観客はリアリティを感じられない。リアルから乖離することにファンタジーの良さがあるはずのに、観客は現実世界に生きている人々なので、あまりの絵空事にはついていけないと言うのも事実なのである。「ブレードランナー」の未来世界も湿った冷たい蒸気に包まれた有機的感覚の世界。クリアで無機的な人工未来都市や「スタートレック」などでまま見られる安っぽい他の星の描写などは噴飯物だったりする。かの「CASSHERN」も同様だった。美しいCGの世界でもそこに豊かで厚みのある空気感がなくてはならない。本来CGは豊かな色彩表現のために使うためのものでもあるので、自ずと奥行きが描写されるはずなのに、わざと色を抜いてみたり、セピアに着色したりするのは愚挙に思える。ゴジラシリーズに登場したGフォース基地、とかく東宝のSF映画のセットも全体的にのっぺりしていて、コンビニの店内のような照明がされているからだが、リアリティがない。俳優の顔に霧を吹きかけたり、油汚れをメイクして見せてもピンとこないのはそのせいである。地方ロケの達人は山田洋次監督であり、「男はつらいよ」組である。短いカットでも、実に上手に雰囲気を作る。カメラマンと照明スタッフの真価の見せ所だ。
「下妻物語」をロケ力(ろけぢから)の観点から見ると確かに下妻市近郊の風景はカメラに収まっているのだが、息吹が伝わってこない。そもそも原作者が下妻を舞台に選んだのが、その「名前」に惹かれたからだそうで、「下妻」というローカル都市を愛していたからではないようなのだ。田舎道を牛を引いて歩いている農家のおじさんを私は見たことがないけれども、ファーストシーンでいきなり牛の糞を踏んづけてしまう深田恭子のようなロリータファッションの娘を見たこともない。「ジャスコ」や「貴族の森」とかいうカフェレストランにも行ったことがあるが、そんな娘を途中の田舎道で見かけたことはない。ヤンキー娘ならいると思うが、ロリータはどうだろう。人物はさておいて先ずはロケ力による空気感である。下妻市内や常総線沿線の点描は確かにあるが空気感が実に乏しい。地元民の生活感が出ていない。単にロケ隊がやって来て仕出しの役者を配してコント撮りました的なパートがあって、楽しいんだけれども、現実感がない。軽トラックで野菜の行商をしている荒川良々がそのパートを務めていて、実に楽しいのだがリアルな田舎感覚に乏しい。お客のお母さんたちもどっかの団地妻のようで小綺麗すぎる。軽トラックの行商はあのあたりの住宅地では見かけないこともないので、あのようなジャスコティックな奥様たちもいるのかもしれないが、どうも下妻ローカルな感じがしない。どこの市の郊外でもありそうな風景である。パチンコ屋のシーンも同様で、ローカル色がなくて面白くない。そもそも下妻市とは駅ビルすらないような街なのである。一両か二両編成の機動車が走る常総線は日本一高い運賃のローカル線と呼ばれているのである。駅前にはスタバどころかコンビニもない。物見高いは人の常、ロケの時は黒山の人だかりだったろうと思うが、じっくりと市内の町並みを撮影して、その空気をきちんと収めてほしかった。その風景にいかにロリータが溶け込まないかをもっとアピールしてほしかった。それでこそ主人公の立場が冴えるというものである。大林監督がかつて尾道の風景を撮り上げたように。とはいわないが、もう少し愛情を持って、地方都市らしさを表現してほしかった。この映画には残念ながら「下妻」物語であるべき必然性がなく、どこの田舎が舞台でもかまわない映画になってしまっている。「下妻物語」の宣伝キャラ化している「牛久の大仏」は下妻市からは上野と川越ほど離れていたりするのである。中島哲也監督は「下妻市」で映画を撮ることよりも最大公約数的な「田舎町」を舞台に映画を撮りたかったのかもしれない。でも、それならばこそ絵にならないような田舎道の延々と続く退屈なシーンを飽きるほど見せて、「退屈な田舎町」の空気をきちんと捉えてほしかった気がする。そうすることで二人の主人公の生き方がもっと輝いたことだろう。
空気感を描かなかったことで致命的な失敗があるとすれば、前述のように田舎では浮いているはずの深田恭子のロリータファッションが劇中では浮いているように見えないことだ。これには理由があって、彼女の周りの普通の高校生たちが私服ではいっさい登場しない。早い話がこの映画に登場する女の子はロリータファッションの深田恭子とヤンキーファッションの土屋アンナだけなので、この二人の格好が普通の高校生からはかなり逸脱しているということが感覚的にわからなくなってしまう。特にフリフリのロリータファッションと茨城県下妻市とのミスマッチ、というのがこの映画の一つの売りのはずなのだが、次第に違和感を感じなくなってしまう。田舎というと閉鎖的で世間体を気にするイメージがあるが実際は都会よりも民情は大らかで、土地も豊かだから……ではない。これは背景となる普通の高校生たちをまるで描いていないからなのである。だから、いつの間にか深田恭子と土屋アンナの二人を観客は受け入れるしかないのだが、その異常性が薄められてしまっていることは否めない。
深田恭子は誰よりも自分を愛する人間として登場するので、友がいない。土屋アンナも「レディース仲間」以外にダチはいない。いや、土屋アンナは暴走族の中にですら心を許しあえる他人を持っていない。寂しい心を特高服で隠しているが、友情を必要としない深田恭子よりもかなり普通の人間である。この土屋アンナのヤンキー娘ぶりが直情的で楽しくて素敵。イタリア語講座の頃は年齢不詳の変なヘソだしねえちゃんにしか見えなかったが、この映画における彼女は素晴らしすぎる。日本の男優はヤクザを演じさせると誰でも何故かうまいものだが、彼女の演技はキュートであり、凛としていている。奇跡的な好演である。今年の映画の新人賞は土屋アンナのものだ。
他人を全く愛さず自分の価値観だけで生きようとするクールな深田恭子が、他人を愛さずにはいられないホットな土屋アンナとのファンキーな出会いにより、絆を結ぶ過程を見事に描ききったところが本作の特筆すべき点である。これは宇宙人と少年が出会って友情が芽生えること(E.T.)よりも希有な奇跡を描いているのである。それをそっと見守る祖母役の樹木希林と「BABY,THE STARS SHINE BRIGHT」社長役の岡田義徳がクライマックスにほどよいスパイスを添えている。この映画で樹木希林が眼帯をしているのは眼病の悪化のせいなのか、心配である。この人の演技には全く凄みがある。この人の充実した存在感は御大が若者映画に「特別」出演する時の見本(田中麗奈の充実ぶりも樹木希林との共演CMのせいではないだろうか)を見るようだ。「リターナー」という凡作を精一杯、リアルな地平に繋ぎ止めようとしていたのは彼女の貫禄によるものである。また映画全体のリズムにアクセントとしてアニメを加えるたのも「キル・ビル」のパクリとか言われそうだが、こっちの方が必然性もありおもしろい。
下妻物語の冒頭は予告編で流れている深田恭子のバイク事故から始まる。その一瞬の走馬燈から物語が紡がれる。その後しばらくセット撮影とモノローグが続くが、次第にロケが多くなり解放されていく。深田恭子の家に土屋アンナが乗り込んでくると、俄に映画が動き始めるのだが、そのスピード(原チャリの)で一気に物語が疾駆し始める。実に爽快である。この爽快感の前にカットされてしまったのが前述の「絵にならないような田舎道の延々と続く退屈なシーン」なのである。しかし、この映画は田舎を舞台としているのではなく深田恭子と土屋アンナの二人を素材とした映画なのだから、このリズムは正鵠を射ている。これでよいのだ。大笑いして元気が出る映画。土屋アンナの頭突きとキックのテンポは必見だ。正司敏江・玲児のドツキ漫才の平成版である。このシチュエーションコメディはかなりしっかりしたものなので、二人の友情を既成のこととして続編を企画し、映画やテレビドラマ化するのも悪くない。仲村トオル、清水宏次郎以来の名コンビの誕生を一作で終わらすのは斜陽が叫ばれて長い邦画界の一大損失である。このブロディ&ハンセンの超獣コンビ(?)級の活躍の舞台が「下妻」であったことを下妻市民は誇りに思ってよい。分別盛りの大人にとっては、原チャリで風を初めて感じた頃を思い出してみるのに、最適な映画でもある。青少年の非行に悩む教育委員のお歴々に無邪気に楽しんでほしいSUPER RANDOM的特選の一本だ。
さて、その後無事に「キューティーハニー」はリベンジした。結果は平凡なセカンドフライのはずがハニーフラッシュ(サトエリのプロポーション?)に目がくらんで落球。記録は内野安打。庵野秀明監督というのは実に平凡な映画を撮る人だったようだが、あの肉襦袢のようなハニースーツには夢がないので反省してほしい。ともあれ芸能人は歯が命なのを忘れないことだ。俳優の歯垢くらいは落とさせるべきである。パンサークロー側は意図的なのかもしれないが、味方にも歯が汚れている役者がいたような気がした。ハニメーションは二カットくらいだったし、まあ黄金の「ナゾータワー」はご愛敬である。よい機会なので実写版「黄金バッド」(1966)を見ていただいて、未来に夢のあった昭和四十年代を回顧するとよかろう。
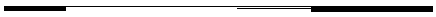
Copyright(C) 1980-2023 SUPER RANDOM Com. All rights reserved