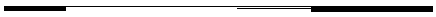
黒澤映画は日本映画の名作とされている。私の場合実際に映画館で見たのは「七人の侍」「影武者」「乱」「生きる」「酔いどれ天使」の5本しかない。残りはビデオで見ただけなので、感想をいうのは烏滸がましいのだが、一度は語りたい巨匠だ。私のリアルタイムの黒澤映画は「影武者」である。ルーカスとスピルバーグ、コッポラが桃太郎の犬猿雉ではないが、黒澤明の元に協力を申し出たという伝説は日本人として誇らしい。当時の黒澤明は製作費を集めることに窮して、前作ではソ連と手を組んだり、この映画ではフランスからの援助を得たりと苦労の連続だった。
日本映画には金がかかる。いや、金がかかっていないと嘆く映画ファンが圧倒的だが、日本で映画を作るには金がかかるのである。だから零細な映画製作会社は十分な資金を投入できず、常に安い作りの映画しか作ることができないのだ。現在世界に誇る北野武の映画は常に低予算である。彼の資質がヨーロッパ映画的だからだが、ハリウッド大作映画に心を奪われている映画ファンは低予算イコール低作として日本映画そのものを歯牙にもかけない。そして日本映画の良さがわからないと口々にいう。実に嘆かわしい。「わかんなーい。」と日本映画を蹴飛ばしてしまう人によい日本映画を紹介することは、女の子に仮面ライダー1号と2号の見分け方を教えるほどに難しい。世界的に評価が定まっている黒澤映画を持ち出したところで時代劇やモノクロ映像ということだけで見向きもしないに違いない。
カラーの現代劇で若者向きと思われるのは「夢」しかない。オムニバスなので気軽に見られるし、作りも丁寧だ。死んだ兵隊がトンネルからでてくるエピソードは怖いものだが、それ以外はどうか。座敷わらし風の雛祭りや狐の嫁入り等ファンタジックではあるが、「世にも奇妙な物語」を見て育った世代にはインパクトは薄そうである。雪女のセットはウルトラセブンの頃の円谷プロ作品のようだったし、鬼のシーンは「大霊界」のような印象すら受けた。全体的に夏目漱石の「夢十夜」と同じように脈絡がない。脈絡がないのはそれでよいのだが、全体的に肩すかしをくわされたような印象がある。CG技術が未発達な時期の作品であることと、低予算なのが惜しまれるが、全体的に「大作風」な作りがしてあるだけで、ジャパン・ホラーになれた若者が怖がってくれまい。復員兵のエピソードも舞台劇を見るような印象で終わりかねない。総じてダイナミズムに欠けているのは晩年の作だから致し方ないか。
時代劇以外では「デルス・ウザーラ」がある。全体的に寡黙な作りがしてあって、冗漫な感じがするのだが、雄大なシベリアの自然が心にしみる。自然派の方、キャンプや山が好きな人にはお勧めである。デルスがカピタンの家で暮らすあたりから早足になってしまい、映画的に失速してしまったような気がする。あの部分をじっくり描いたところで話は盛り上がらないので仕方がないところだが、構成的にもう一工夫あってもよかったのではないだろうか。デルスを街につれてきてからの描写が淡白すぎてバランスが悪い。とはいえ文化を超えた人間同士の魂のふれあいを描いている点では出色である。カルチャーギャップを真摯に描いた佳作だ。
現代劇では「天国と地獄」。シネスコでハリウッド大作のような感じ。特に冒頭の贅沢な部屋の中から一向に出ない作劇は、出演者たちの密室であり舞台を見ているかのようである。だから悪いというのではなく、これがよいのだ。「十二人の怒れる男」のようなもので、切迫した状況を実にねちっこく描いている。中盤はがらりと変わってカメラが外に出ての犯人探しに転じ、刑事の尾行、追跡とダイナミックにメリハリが利いている構成。これを犯人の動機と絡めて社会派推理劇のように論じる向きもが、これは一級の娯楽サスペンス映画である。捜査会議のシーンを「飢餓海峡」「砂の器」「人間の証明」などの大作刑事映画と比較してみるのも一興。
「生きる」は私が初めて映画館で涙を流した映画である。この映画も大胆な構成で、前半は余命幾ばくもない主人公が生き甲斐を見つけるまでの迷走を描き、後半は主人公の通夜の席が舞台となる。「いや、やればできる。やる気にさえなれば……」と絶望の淵から立ち上がる主人公に、背後ではしゃぐ女子学生たちの合唱がそのままBGMとして被っていくシーンは何度見ても肌に泡たつ感激を与えてくれる。弁慶高校の牛若の予告投球のようだ。ど真ん中の直球である。こんな球はおっかなくて普通は投げられない。座右の一本。挫けそうになった時に見ると元気が出る。個人的にはズボンの寝押しをするシーンや、息子の名前を呼びながら息子の少年時代を回想するシーンにも泣ける。
時代劇といえば「用心棒」と「椿三十郎」。この明快な時代劇は殺陣こそ迫力がないものの、躍動感にあふれていて痛快の極み。「用心棒」の方が迫力があるが、より明朗度が高い「椿三十郎」を推す。サムライ=ミフネのイメージを外国人が持つのはこの2作によるのだろう。その後ひたすら三十郎もどきの侍を演じ続けたのは役者として三船敏郎の怠慢というか、サービス精神の成せる技か。スターウォーズシリーズに多大な影響を与えた「隠し砦の三悪人」。この敵中横断三百里(古いたとえだなぁ)ものも面白さは殺陣よりもストーリー運びにある。ただ逃げてるだけの「エネミー・ライン」や本当に脱出する気があったのかと疑わしい「ランボー2怒りの脱出」や「ランボー3怒りのアフガン」に比べて、実に起伏に富んだ芳醇な脚本である。
「蜘蛛巣城」と「乱」は、それぞれ「マクベス」と「リア王」という世界共通語を翻案した時代劇。「蜘蛛巣城」はラストの矢襖となるミフネの死が印象に残る。あれ以上のハリネズミ状態といえば市川監督の「火の鳥」における若山富三郎くらいしか思い浮かばない。「乱」はあまりにも虚しい結末で、あれが監督の狙いなのかもしれないが、虚しすぎるので嫌い。「影武者」のラストも虚しいものではあるが、あれは悲壮感が叙情的に描かれているので美しい。戦闘シーンがないのが困りものだが、「戦国自衛隊」を馬鹿にしていた監督だから、中途半端な合戦は作りたくなかったのだろう。角川監督の「天と地と」におけるような合戦ならない方がいいので、潔く切り捨ててしまった監督は偉い。その分を「乱」でということだったようだが、石灰粉ばかりが舞っていて、「乱」の合戦もちょっと弱い。NHKの大河ドラマと同工異曲な合戦シーンは撮りたくなかったのかもしれないが、所詮、合戦なんていう大群衆シーンをエキストラと石灰の粉だけで撮ろうというのが無理なのである。
さて、どん尻に控えしは「七人の侍」。三時間の超大作は54ゴジラと同年に東宝が公開したということでさえ、伝説の一部でしかあるまい。完璧な娯楽映画というものがあるとしたならば、テーマとアクションが一体となったこの作品こそが神の領域に近いものである。どのシーンを見ても面白い。侍たちが集まるまでの前半が戦いよりも面白い。こんなに面白くてよいのかというくらいで、逆に言えば面白くないシーンがない。木賃宿の床にこぼれた米を一粒ずつ集めるシーンの、白米の美しい透明感。さっきまで百姓たちを罵倒していたならず者たちが、侍に食ってかかるときの威勢のいい啖呵。カットのつなぎや演技者のたたずまいまですべてが見所である。それはナイアガラの滝を見て水の一滴までもに感動できるようなものだ。最後の合戦も圧巻の一言に尽きる。ただし、殺陣はうまくない。七人の侍だけが達者な殺陣を使うという演出でかまわないと思うのだが、残念ながら彼らの殺陣には迫力が感じられない。これだけが「七人の侍」の完璧を阻んでいる。しかし、それすら感じさせないアクションのつるべ打ちとスペクタクルなカメラワークで怒濤の戦いを見せてくれる。三時間という時間のストレスさえカタルシスに変える、壮絶な合戦シーンである。「プライベート・ライアン」や「スターリングラード」の実録風戦闘シーンは飛び道具だが、こちらは白刃の肉弾戦。氷雨のような土砂降りの雨に打たれた白兵戦である。CGで合成したのではない白い吐息、汗が全身から湯気となって沸き立つ躍動感。侍や百姓も観客をも巻き込んで一体となり夢中で戦うラストファイト。映画館で見れば至高の三時間が提供されるに違いない。この映画も「生きる」と同様に、見た後で元気が沸いてくる映画である。この一作を見ずして日本映画をつまらないなどと言ってはいけない。
「ロード・オブ・ザ・リング 二つの塔」の合戦シーンに雨が降り出した時に「七人の侍」へのオマージュかと思ってニヤリとした。
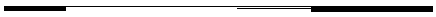
Copyright(C) 1980-2023 SUPER RANDOM Com. All rights reserved