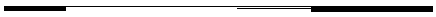
青春推理小説という言葉は死語である。というよりも、このような分類自体がナンセンスだったと言ってもよいかもしれない。70年代頃から始まったハイティーンが活躍する推理小説のことを指すのだが、私の認識の方を先に挙げておこう。この名称は乱歩賞作家である小峰元の「アルキメデスは手を汚さない」を嚆矢とするものだ。高校生前後の年代が主人公であり、その年代の若者にありがちな思春期の感情の揺れがきちんと描けている、青春小説的要素の濃厚な推理小説のことである。松本清張の「高校殺人事件」(「赤い月」)もあったが、どうにも青春の哀感を描いているとは言い難かった。中高生向けの学習雑誌等に連載されていたからといって青春推理になっているかというとそうではない。高木彬光の「我が一高時代の犯罪」の方が、当時の若者らしさや世相をとらえていてトリック的にも楽しい。器用な西村京太郎には「俺たちはブルースしか歌わない」もあったが、青春推理としては老成した感覚の小説だった。青春推理という分野は人生の出発点に立つ若者のとまどいや恋愛などが瑞々しく描写されていてほしい。栗本薫や梶龍雄の初期作品もその味わいを持っていたと思う。東野圭吾の「放課後」は青春推理っぽい作品ではあったが、瑞々しさが足りなかったように感じた。テレビドラマ化されたときは山下真司(太陽にほえろのスニーカー刑事)が主演だったと思うが、平板なドラマだった。高校生さえ出しておけば青春推理かというとそんなことは全くないのである。大沢有昌のアルバイト・探偵シリーズは高校生が主人公のスパイアクションものであるが、娯楽小説に過ぎない。(念のために書き加えておくと、これは賛辞である。アルバイト・探偵シリーズは変なたとえだが、ルパン三世や直撃地獄拳的な面白さを十二分に備えている。)私が青春推理というジャンルにこだわりがあるのは、つまり私自身が高校生の頃に同年代の主人公たちが活躍する推理小説を希求していたと言うことなのだろう。当時は推理小説は社会派推理が幅をきかせていた直後で、横溝正史が復活しはじめた時代だった。中高生にとって主人公に感情移入ができる推理小説が少なかったからに違いない。
赤川次郎は青春推理の騎手として早くから注目されていた。「死者の学園祭」から女子高生を主人公にしたシリーズ。三毛猫シリーズや幽霊シリーズにしても人気だった。仲良し女子高生三人組が登場する悪魔シリーズや三姉妹シリーズなど楽しいシリーズものは多いが、やはりミステリー的興味にしろ、青春小説としての妙味にしろもの足りない。赤川次郎の描く高校生像は非常に古い。文章は巧いのだがクラシカルで観念的なステレオタイプの登場人物ばかりだった。「お話」の中の「女の子」や「男の子」が登場しすぎてリアルではない。「セーラー服と機関銃」や「探偵物語」等、映画化された作品も多いが推理小説としての収穫がない。薬師丸ひろ子を完璧なアイドルにしたのが「セーラー服と機関銃」である。相米監督とのベストマッチは「翔んだカップル」に譲るとしても、「セーラー服と機関銃」の薬師丸ひろ子は自らの最も輝いていた瞬間を永遠にフィルムに焼き付けることに成功した。アイドルの持つ魔性が炸裂した角川映画随一の傑作である。もちろん映画的にはてんでんばらばらで見事に破綻しているのだが、そんなことを微塵にも感じさせないパワーがこの作品には満ちている。三国蓮太郎の妙なキャラクター造形といい、とかく「ぶっ切れている映画」だった。機会があればじっくりと鑑賞して暗い気分を満喫してほしい。赤川次郎の読みやすい文体は有象無象に模倣され、昨今のシナリオ風ジュブナイルの氾濫につながってしまった。氏にとっては不本意だったかもしれない。
若い感覚を一生懸命模索していた作家は小峰元だった。彼の描く悪漢小説も確かに古い観念的な若者像が多かったが、新聞記者感覚を生かして、若者層に積極的に取材していたとも思われる。「社会人として一人前になることとは、全くお世話になっていない他人に対して、お世話になっています。と言えることだ。」とは蓋し名言である。晩年の作品まで常に若者を主人公として現代の青春小説を描くことに挑んでいた。しかし、彼の場合は特に晩年の語り口が古めかしかったため、若い読者の支持は得にくかったと思う。小峰元の奇跡の傑作は「ディオゲネスは午前三時に笑う」である。青春小説らしい設定と乱歩賞作家らしい密室物の融合。青春推理小説の古典として珍重されてよいだろう。今となっては入手が困難だろうが、この一作だけは読んで後悔はしない。比較的入手が容易なものは乱歩賞受賞作「アルキメデスは手を汚さない」だろうが、姉と弟という設定が似ているだけで、小説としては「ディオゲネス……」の方が優れている。その後、小峰元は軽い傑作「プラトンは赤いガウンがお好き」や「ヒポクラテスの初恋処方箋」をものにしている。ミステリの要素はかなり低いが絶妙に楽しい小説だった。特に前者の主人公、パトラ(というニックネームの女子高生)にはたいそう魅力的な性格を与えられている。森雅裕の「さよならは2Bの鉛筆」の鷲尾暁穂ほどアグレッシブな娘ではないところがリアルですらある。
「ぼくと、ぼくらの夏」の樋口有介辺りまでが私にとっての青春推理小説かもしれない。この作品は和久井映美、蟹江敬三主演で映画化されている。映画の舞台が茨城県なのも私にとっては慕わしい。沢田研二をはじめとする元グループサウンズの面々が、大量に特別出演しているという不思議な映画だった。ミステリ的には興味が薄いが、正当な青春映画の作りがしてあった。数少ない茨城の観光スポットを点描した映画としても貴重な存在である。ちなみに「ビー・バッブ・ハイスクール」における中山美穂の母校は茨城県水戸市の某高校の校門が使用されているそうだ。
閑話休題。最近、私は推理小説そのものが実は青春小説だったことに多少なりとも気がついてしまった。推理小説は基本的に正義が実行される小説である。その正義感はどこからくるのかというと「ワカモノ」らしい潔癖性からくるもののはずである。青春推理の衰退は「ワカモノ」が潔癖性を失ったことが最大の要因なのかもしれない。現実を受け入れて享受するだけという若者気質が青春推理というジャンルを殺してしまったのではないか。80年代以降のカラオケ文化やテレビゲーム文化といったようなマスメディアによる画一化。自己不在の自己主張。自我のない自意識過剰。それらの社会的ムーブメントによってこそ青春推理は死滅したに違いない。青春小説は時代と寝(理性を捨て)ればよいが、青春推理はそこに厳然たる理性を必要とする。青春推理とは合理的であるべき推理小説と不合理であるべき青春小説との微妙なバランスの上でしか成り立たないものだったのである。
「純粋に真理に到達したいだけなんです。」とうそぶく浅見光彦的な探偵の動機というのは青春小説の主人公に相応しいものではある。問題は現実の社会との相克によって無惨にその正義感が傷つけられるという要素を配することができるか否かにある。刑事局長の弟という印籠を振りかざす光彦は、その悩みから解放された現代の岡っ引きに過ぎない。犯罪者自身の自決を見逃したりするのは、責任逃れのナルシストに陥りかねない。そのために浅見光彦はシリーズキャラクターたり得ている。重大な犯罪に絡んだ人間としての業の深さを背負わない以上、浅見は青春推理の世界の住人とは言えない。浅見光彦シリーズが次第に本格推理からキャラクターものにシフトチェンジしてしまったのもむべなるからである。とかく本格推理というものはゲーム感覚が溢れているほど、児戯的な要素が深い。故に新本格の新鋭たちへの批判は常に開口一番筆力不足というレッテルだった。それに対する反駁から過剰にパズルに走ったりする作品もあったようだが、批判はお門違いであり、パズラーを目指すものに対してドラマを求めることは見当違いである。純粋な謎解きこそがパズルミステリーの本道なのだと突き進む作家たちにドラマ性を求めてはいけない。とはいえ生けるものの究極の着地点である「死」を扱う以上、リアルに描けば描くほど、それは登場人物の人生を描写するものでなくてはならない。偉大な文学作品が構造上ミステリの様相を帯びるのは、人生こそが最大のミステリであるからに他ならない。たとえ奇をてらったトリックが行われたとしも、それを実行するのは血の通った人間であるはずなので、その動機や人間性がきちんと描かれていなければ説得力は得られない。本格推理は本格心理小説でもあるべきなのである。
閑話休題。「我が青春の推理小説」を語ってみよう。私に唯一、リアルタイムで主人公たちと年を重ねるという得難い経験を与えてくれた作品群。それは日本アニメの開祖的脚本家、辻真先の「キリコ&薩次シリーズ」である。ここに登場する高校生像は赤川次郎のそれのように古びていない。かなり現実味あるイメージがある。マンガチックであるという評価もされるだろうが、それが悪いというイメージに結びつかない。70年代はアニメが若者文化として社会的に認められつつあった時期である。主人公たちが漫画的キャラクターであるということは、それだけ当時の若者に受け入れられる造形であり、ある意味ではリアルだったのだ。(2000年代の若者の思考や行動がアニメチックで無機質な面ばっかりが目立つのは、日本のアニメ文化の功罪ではある。)
青山の自宅がスーパーマーケットを経営していたことと、自身がスーパーウーマンであることから生まれたニックネーム「スーパー」を持つ可能キリコ。「ポテト」というニックネームはその顔と体型からという牧薩次。直情径行の美少女であるスーパーと鈍牛的ポテト。派手に事件を引っかき回すヒロインと冷静に謎解きに徹するヒーロー(?)。このマンガチックなフォーマットに手塚治虫直伝のスターシステムを採用した辻ワールド。ハッタリとケレン溢れる壮大な叙述トリック。常に流れる演歌的青春への鎮魂。私は辻真先の最もいい時期に一緒に生きられて幸せだったと思っている。後に可能キリコの兄である克郎(の恋人)の活躍を描くシリーズもできたが、その頃にはミステリとしての興味はなくなっていた。
徳間書店から刊行された「合本・青春殺人事件」。これには朝日ソノラマ文庫時代の「仮題・中学殺人事件」「盗作・高校殺人事件」「改訂・受験殺人事件」の三作が収められている。この三作はどれも傑作であり、それぞれに見所がある。「キリコ&薩次シリーズ」としては「宇宙戦艦富岳殺人事件」までが読みどころと言っていいだろう。シリーズを離れたところでは推理作家協会賞を受賞した「アリスの国の殺人」。よりも私としては「離島ツアー殺人事件」が印象深い。昭和60年代の氏の活躍に直木賞が冠せられたり、「キリコ&薩次シリーズ」が実写化されなかったりしたのが不思議でならない。早見優主演で映画化された「村で一番大きな首吊りの木」は原作自体が凡作だったので、いかがなものだったのだろうか。
ちなみに辻真先脚本のテレビアニメで私が推すのは「サイボーグ009」における第16話「太平洋の亡霊」である。小杉太一郎作曲、東映動画中最も涙腺を揺るがす女性コーラスが流れる。ビデオで確認してもらいたい。これをSF反戦娯楽戦争映画の名作と呼んで誰憚ることはない。
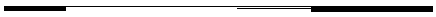
Copyright(C) 1980-2023 SUPER RANDOM Com. All rights reserved