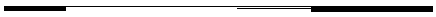
2004年邦画史上最強打線。テレビアニメの実写映画化に果敢に挑む四番打者は「DEVILMAN」になった。「デビルマン」は「あしたのジョー」と同じ頃に少年マガジンに連載していた泣く子も黙る恐怖まんがである。テレビとタイアップした企画で、テレビは辻真先が巨大ヒーローアニメとして成功させ、まんがは永井豪自身が周囲の思惑を見事に裏切り、壮大な黙示録に仕立て上げてしまった。
永井豪が石ノ森章太郎のアシスタントであったことはよく知られている。石ノ森が「サイボーグ009」や「幻魔大戦」で描きたかったクライマックスを「デビルマン」が先にやってしまったので、石ノ森の構想が狂い、「天使編」を完成させることが出来なかったという逸話を聞いたことがあるが、真偽のほどはどうなのだろう。造物主が地球外生命体であり、人間が神と崇めるそれと邂逅するというのは今や珍しいテーマではない。(トンデモSFの決定版、高橋克彦の「総門谷」も同じだが、あちらは西洋版魔界転生の要素がてんこ盛りで十二分に面白い。あれこそ映画化して欲しい。)石ノ森章太郎原作の「仮面ライダーBLACK」には創世王なる敵役が登場した。「仮面ライダーアギト」も神らしきものと戦っていたようである。
しかし「デビルマン」も人類滅亡に至るハルマゲドンを描いているが、造物主対人類ではなく、地球外生命体対人類の図式でもない。言わば先住民族と現住民族との抗争に過ぎない。デーモン族は地球の先住人類的な存在であって、同じ地球に生まれた種族同士の生存競争を描いたのが「デビルマン」なのである。神=造物主的な地球外生命体はデーモン族対人類の勝者に天罰を下すべく飛来する、いわばシード選手なのだ。この映画のキャッチコピーの一つ、「愚かな生き物よ。神はいたか。」というサタンの問いかけはピントがはずれている。サタンは堕天使であり、かつては神の身内である。神が地球外に存在することはサタンだけが承知していることだろう。「デビルマン」世界で、人類が夢想している神とはデーモン族を神格化させただけにすぎず、真の神と邂逅する前に人類は滅亡してしまう。
テレビアニメ版は昭和四十年代のテレビ放送を意識してか曖昧な結末でお茶を濁してしまったのは良識と言える。もしもこの原作通りの展開をさせたとしたならば少年少女は言うに及ばず、社会に強烈なトラウマを投げかける作品として大問題になったはずだ。何しろ、全人類滅亡という逃げ場のない絶望をリアルに表現してしまったのだから。まんが「デビルマン」の素晴らしさは「巻き込まれ型」のストーリーが加速し、ヒーロー物の枠を打ち崩し、単行本わずか五冊において人類の終末を描ききってしまったことにある。これを二時間足らずの劇映画で表現するのは蛮勇以外の何物でもない。しかし「DEVILMAN」は突如起こった2004年のアニメ実写化路線の中ではただ一作、フィルモグラフィーに実績のある那須博之・真知子夫妻が監督と脚本を担当している。果たしてその挑戦は評価できる仕上がりとなっていたか。
予算の問題と俳優の演技能力以前に、那須夫妻の力不足を指摘されても否めない。貧相な炎の描写から全てが始まる。暖炉の前の子役の演技のまずさ。あり得ないダイナミックな絵だけの絵本。続く陸上競技部の練習シーンの稚拙さ。不動明がばてるシーンのやる気なさと飛鳥了のランニングシーンのいい加減さが、センスのない学生映画にありがちな無演出ぶりで、人類の滅亡を予兆させる……というより、これから始まる2時間の悪夢を観客に予感させてしまう。とても了が陸上部のエースには見えない。陸上と不良というのは一番不似合いなスポーツに思える。(それとも不了という親父ギャグで、この話に登場する了は了ではないという暗喩か?)伊崎兄弟が未熟なだけではなく、那須監督の演出力が至らないからである。「ピンチランナー モーニング娘。」なら笑って許される走りも「DEVILMAN」では許されまい。人類の滅亡と駅伝部の廃部が同等の演出で許されるはずがない。那須真知子にアニメ脚本の経験があるかは知らないが、アニメなら許されるセリフも達者な声優に命を吹き込まれれば通用するかもしれないが、「ヤンヤン歌うスタジオ」級の芝居にかかっては耳障りな雑音にしかならない。不動明と飛鳥了という最も重要な二人に演技経験のないアイドルタレントを起用したのは那須監督としても本意ではあるまい。しかし常識ある映画人が積極的に組むような配役とは思えない。主要キャストのすべてに実力ある役者を配置しなかった責任は誰かが負うべきである。芝居をしていたのが酒井彩名だけという作品を劇場公開しては東映の三角マークが泣く。白刃と硝煙で守り抜いてきた大東映の金看板をなんと心得る。
那須監督は「ビー・バップ・ハイスクール」で無名の新人、仲村トオルと清水宏次郎をスターダムに乗せた男である。主要キャストに思うような役者が揃えられなかったのなら、せめて脇に光るキャスティングをすることはできなかったのか。素人を使う術にも長けていた監督のはずなのに、仕出しのタレント予備軍をそのまま並べるだけとは芸がない。明を悩ませる同級生のいじめっ子三人組が普通のハンサム揃いで個性がない。(男気もないから明の子分になって、牧村家を守ることもしない。)ミーコをいじめる三人娘も普通の美少女たちに過ぎない。チビもいなければデブもいない。出っ歯もいなければノッポもなく、ブスもいなければメガネもいない。全ての登場人物が平板で没個性的で十人並みだ。かつての「ビー・バップ軍団」のような超個性的な素人を何故起用出来なかったのか。今の男の子は同じようにおしゃれで、女の子はみんな整形しているので、どうしても無個性になってしまうということなのか。否、きちんとオーディションして選んだ俳優を使っていないだけだ。エキストラとの区別すらつかない俳優を使っているのは、そこに監督やスタッフの映画への愛がないからだ。端役にしろ、主役にしろ演技の未熟さは本人の素の魅力でカバーさせるべきなのに、素のないマネキンを幾ら並べてもそこに魂が宿るはずはない。宇崎竜童・阿木耀子といえば元祖・仮面夫婦として長い芸歴を持っている。この二人が牧村美樹の両親を演じてはいるが、二人の最期の会話も悪ふざけとしか思えない。嶋田久作の出演は帝都物語への献辞なのか。殺される悪魔人間の一人にKONISHIKIが混じっていることも、ニュースキャスターがボブ・サップなのも無意味きわまりない。(「ビー・バップ・ハイスクール」にも藤波辰巳が出ていたからいいのかも知れない。)とはいえ、いつもの芝居をしていたのがきたろうと小林幸子だけという状況では、人類が滅亡してしまうのも無理はない。
「七人の侍」で最強のサムライ・久蔵を演じた宮口精二は剣道すらやったことがない。彼が監督にそのことを正直に申し出たところ、黒澤明は「心配するな。俺が撮るのだから。」と笑ったという。次々と素人俳優を使って傑作をとり続ける大林宣彦監督。素人俳優を強烈に映画の人に仕立て上げてしまう相米慎二監督。彼らの功績を前に全ての失敗を俳優のせいには出来まい。若手俳優に伸びる可能性はあるが、ベテラン監督の失態は今後の創作活動の致命傷になるだろう。
私は原作原理主義者ではない。どんな映像作品を持ってこようが、「原作にはかないませんよ。」と原作を崇めることはしない。梶原一騎原作の「巨人の星」「タイガーマスク」は原作のまんがよりもテレビアニメの方が傑作だ。実写版にも実写ならではの楽しさがある。無論、失敗作も多いが、「ビー・バップ・ハイスクール」は面白いし、「ルパン三世 念力珍作戦」も捨てがたい魅力がある。しかし「DEVILMAN」は映画としての拙劣さが目立ち過ぎる。デビルマンやサタンの造形は好みの問題だろうが、実写と融和しているレベルでもない。自慢のT-ビジュアルというのが合成カットの中にアニメをサブリミナルさせる技法のことを指すだけのことだったならば、まだハニメーションの方が意欲的な取り組みだったと評価できる。
「デビルマン」は悪魔の話ではなくて、人間の話だ。人間の心が描かれなくてはならない。「DEVILMAN」は人間を描こうとしているだろうか。キャラクター設定が原作とは大きく異なっている。原作の不動明は非力なやせっぽちであり、牧村美樹に守られているような存在だった。しかし、彼の純粋な正義感が悪魔の心を凌駕し、肉体はデーモン、心は人間という悪魔人間(デビルマン)が誕生するのである。デーモン族から人類を守るべく、親友とたった二人ぼっちで立ち上がるのだ。なればこそ伊崎央登の貧弱な肉体は不動明そのものである。表情も悪くない。それなのにデビルマンになる前と後との性情の違いがきちんと演出されていない。内面で表現できないのならば、せめて言葉遣いや制服の着こなしを変えるくらいの目に見える演出は施すべきなのだが、そもそも明が純粋な正義感の持ち主だったように描かれていない。悪魔人間になった後にワイヤーアクションバリバリで不良たちを撃退する明だが、この場合は敏捷性よりも力強さを演出するべきで、演出プランにミスがある。また真っ昼間に校舎に囲まれた中庭でリンチを仕掛ける不良はいないはずなのに、強行にロケしているのはスケジュールの都合か、それともスタッフのやる気のなさの表れか。そもそも高校三年にもなってあんな不良像やいじめの仕方はあるまい。不良たちが中学の時の飛鳥了指切り伝説を知らないなんてのもあり得ない。ロケ地で言えば物語の舞台がいつも東京でなくても良いのだが、そもそも静岡市を舞台にしてハルマゲドンを描くというのは明らかなスケールダウンに思えて意図がよくわからない。何故、静岡でなくてはいけないのか。
デビルマンそのものの造形は原作とテレビアニメを合体させてS.I.C.風味でCG化したもので、好き嫌いの問題であろうから言及はしないけれども、明とアモンの中間形態の特殊メイクがデーモン木暮の域を出ていないのは見ている方が恥ずかしい。デーモン閣下もきっとお嘆きに違いない。その時の「声色」も子供だましの領域に過ぎず、聞き苦しいものだ。変身後のアフレコだけでもせめて声優を使うべきだった。デビルマン対シレーヌの戦いも動きはカット割りや駒落とし、CGエフェクトで誤魔化しても、声が演技者自身のままなので脱力感が激しく、とても視聴に絶えない。声にもコンピューターでエフェクトをかけてCV(コンピュー・ボイス)合成をするべきだ。少なくともただ一つの見せ場と言えるデビルマン対シレーヌの空中戦はより美しく、華麗に(無言で)決めて欲しかった。
飛鳥了の人物設定にはクールさや思慮深さが全く描かれていない。授業に出てなくとも、部活にだけは出ているという高校生ぶりも意味不明で納得がいかない。金髪なのに眉毛が黒いという描写では了がただのヤンキーにしか見えない。(しかも幼稚園の頃から金髪に染めているので筋金入りのヤンキー家庭に育ったらしい。まぁ、親父が本田博太郎ですから。)原作の了は確かに不良少年だが、染髪した頭のてっぺんだけが黒いだなんて見っともない格好はしてはいない。第一、ハーフで根っから金髪のニヒルなクールガイだ。了がサブマシンガンを両手に悪魔特捜隊に戦いを挑んでいくシーンは、ジョン・ウー監督作品の恥ずかしいパロディであり、ガンアクションといえる代物ではない。往年の新春スターかくし芸大会のドラマみたいだ。エピソード的にも尻切れトンボに終わっている。原作では銃身を切りつめたショットガンで必死に武装していたのに、映画ではどこからサブマシンガンを手に入れたのやら、説明すら一切ない。クライマックスで教会に登場する了のフルショットもセンスがない。セリフ回しの稚拙さに耳を塞いでも、ビジュアルが貧相なのはスタッフの責任である。肉体で演技をさせるという当たり前のことを演出しないようでは、那須博之監督は一体、なんのために監督を引き受けたのか。大魔王サタンの世を忍ぶ姿が、あんな佇まいでよいはずがない。了にしろ、明にしろ不要なアップが多すぎるのは「アイドル映画を撮れ。」との社命からなのだろう。しかし、アイドル映画に徹するならばアイドルをかっこよく撮らなければ、それだけで失敗のはずである。この小僧たちは見事にカッコ悪い。ファンはお気に入りのアイドルの未熟で恥ずかしい姿を銀幕に晒されても怒らないのだろうか。PG-12の指定を受けたのは、素直な子供たちに王子様は裸だと指摘されないためなのか。
原作での了は人類を救うために親友・不動明と二人きりで、デーモンと戦う決意をし、行動を開始する。デビルマンはそのような形式のヒーローものとしてスタートした。しかし了の正体はデーモン族の長である大魔王サタンだった。本来の記憶を封印して、人間を探るべく飛鳥了として人間界に紛れ込んでいたサタンは、自己の記憶を取り戻すまで人間・飛鳥了として明とともにデーモンと戦っていた。しかし、飛鳥了=サタンという伏線を映画の中では早く出し過ぎていたた。観客はそのことを見る前から知っているのだが、映画の中であまりにも前提として画いている。少年時代から既にモンスターたちを仲間と称し、中学時代には自らを悪魔であると漏らしている。デーモンが民衆を襲っているシーンに遭遇しても、(サタンだから)人間を助けようとはしない。(サタンだから)無辜の人間を警官に化けて射殺したり、悪魔人間を射殺する悪魔特捜隊の隊員を射殺したりする。つまり、了は人間を助けるためにデーモンを殺すことは一切せず、(サタンだから)人間だけを殺し続けていた。了には元々人類を救おうという悲壮な意志など(サタンだから)欠片もない。原作の了とは全くの別人であるのはよいとしても、人間の感情を知ったことで悩むというキャラクターの深みがそこには存在しない。
了が明を悪魔人間にしたのが、人類の救世主にするためでなかったとしたら、いったい何のためなのか。映画の観客は了(サタン)自身の口から「幼なじみの明を殺さずに仲間に加えたかったからだ。」と知らされる。砂遊びで作った「バベルの塔」を二人が雨から守ろうとした少年時代のエピソードがあの結末にどんな詩情をもたらしたのか。「バベルの塔」は人間の思い上がりに神罰が下る話だ。「DEVILMAN」になんらかの神話的要素を挿入したかったと言うことなのか。そもそも「デビルマン」の世界には神対悪魔という対決の図式はない。元々神なんていない世界なのだ。原作にない映画ならではの+αを探すと「明と了は二人で作った砂の塔を守りたかった…」に尽きる。ここに多分、那須夫妻は彼らなりのテーマを全精力を注いで表現したに違いない。しかし、実際には「バベルの塔」を明と了が二人で雨から守ることはなく、了は「バベルの塔」を叩き潰してしまった。了には明への一片の情はあったものの、人類への親しみは芽生えなかった。この「バベルの塔」が地球で生まれた生命の暗喩と解釈して欲しいのならば、那須夫妻の完全な表現力不足である。ラストに生き残る二人の描写が新世界のアダムとイヴだというのは新境地ではあるけれども、感動を呼ぶと言うよりはよくあるB級映画のサプライズみたいなもので、映画のスケールを矮小させている。
東映トップタイトルの彷彿とさせる岩場の上で、サタンと明の永遠の別れが描かれる。映画では二人の友情物語としての帰結が描かれる。ここで了は「明が笑った。」と喜びつつ、今まで笑わなかった了が初めて涙ながらに笑う。ここに感動のツボを那須監督は置いたようなのだが、私には意図が読みとれない。そもそもサタンは両性具有である。「デビルマン」のサタンも両性具有であり、サタンは明を愛してしまう。「デビルマン」はサタンの片思いの悲恋が人類の終焉に一抹の詩情を誘うのだが、映画は友情(それとも同性愛?)物語に終始してしまった。原作をなぞれといっているのではない。原作が一番良いとも言わない。しかし原作以下のものを作ることには映画としての意味がない。まんがは永井豪一人が作ったものである。それを何百人もがかかって、彼のイメージを貶めることしかできないのでは不甲斐ない。
牧村美樹のキャラクターも永井豪作品によく現れる純情なお侠なヒロインとしては描かれていない。平凡な女子高生として描かれていて、幸せな夫婦生活を夢見たり、朝帰りの明とベッドインしたり、特捜隊に包囲されている中で明とキスしたりする美樹は物足りない。永井豪ヒロインの持つ清浄さはその潔いヌードシーンに顕著に表れる。オールヌードを披露しても決していやらしくない。あだち充ヒロインの場合は、あだち充の視点がいやらしい中年男の視線そのものなので、することなすこといやらしく見えてしまうのだが、永井豪の視線はそんなレベルを逸脱している。あたかも神の視点のようだ。そこにはありのままの裸があるだけで、それをいやらしいと考えるのは考える人間の品性がいやらしいからに過ぎない。あっけらかんとした裸の肉体がそこにあるだけなのである。原作のシレーヌ編では美樹が入浴中にゲルマーに襲われるのだが、決していやらしい場面ではない。牧村美樹には人類の希望が託されている訳なのだから、清らかなイメージがそこにはある。少年まんがだから描けた聖なる存在が牧村美樹だったのだが、酒井彩名の肉体はどうしても現実の生々しい女子高生を描かずにはいられない。この映画ではいじめられっ子だったミーコに、聖なる部分を作劇上どうしても奪われてしまう。酒井彩名がどう健闘しても、そこに永井豪ヒロインの存在感を醸し出すことは出来ない。
映画ではアモンとシレーヌをかつての恋仲だったような設定を加えている。それも悪くはない。しかしシレーヌの登場はシレーヌ人気に乗っかっただけの羊頭狗肉なものになってしまった。シレーヌ編は「デビルマン」では活劇部分の唯一最高のエピソードであり、ヒーロー物としての体裁と「デビルマン」の世界を見事に融合させたハイブリットな名編なのに、映画ではるまるカットされても気が付かないくらいに本筋に関わらぬ無意味なものになっている。ジンメン編の原作は明と心を通わせた少女との決別が泣かせる好エピソードだが、映画ではその少女役を明の友だちに振り替えていた。その友だちはいち早く飛鳥了=サタンに気づき、明に警告を発する役割を持つものの、観客に好感を持たれるような人物でもない。明はためらうことなく、その友だちの顔面を一撃でうち砕きジンメンを倒す。ジンメンというデーモンのキャラクターを全く生かせていないために、明の痛みが観客にまるで伝わらない。それどころがジンメンの口にから原作とはまるで逆の設定が語られてしまう。「デーモン同士は殺し合うことをしない。」人類滅亡後はデーモン族によって地球は争いのない平和な楽園となることだろうが、この付加された設定の先を考えると物語が破綻することに脚本の段階で気がつかなかったのか。人類を滅亡させただけならばともかく、動植物全てが死滅するカタストロフの後ではデーモン族とて生きていけまい。
シレーヌの映画版デザインは誰がやったのかは知らない(サトエリハニーと同じデザイナーらしい)が余りにも醜い。シレーヌが羽を畳むとそれが帽子に、ボデイはワンピース水着姿になる。羽を広げると羽毛のブラジャーが胸に貼り付き、ワカメちゃんパンツのセパレーツ水着姿になる。シレーヌは美しきデーモンではなかったのか。富永愛の裸など見たくもないが、シレーヌは凛として一糸まとわぬ全裸でなくてはならない。強く、気高く、美しいシレーヌは自分を隠したりしない。富永シレーヌはこの映画を象徴するような姑息で、惨めな姿を晒している。シレーヌは美しく、かわいく、恐ろしく、野性的で、熱いデーモンであって、映画のように無表情なでくの坊ではない。シレーヌの手袋に縫い目があったり、不用意に羽が抜け落ち過ぎたり、と首を捻らざる得ない描写が続き、しかもデビルマンと決着をつけるでもなく、唐突に物語からフェードアウトしてしまう。少なくとも明が富永シレーヌに手を引かれて。のこのこついて行くシーンの無芝居ぶりは幼稚園の発表会並みの演出だ。シレーヌを愛するファンは生涯、この屈辱を忘れないに違いない。
デーモンが多い国はデーモン国家と認定され、ミサイル攻撃をされる。国家が抵抗すると全面戦争を仕掛けられるという形で一気に人類の滅亡が加速する。要するにアメリカがデーモン国家と断定すればその国にミサイル攻撃をしても許されるというのが「DEVILMAN」の世界。アメリカとイラクの戦争を連想すれば、全く違和感がないのは現実が既に「DEVILMAN」と同じであるということで実に悲しい。大戦下の日本国内でも特高が思想犯を取り締まっていたのだから、日本が世界と戦端を開いているはずなのに、悪魔特捜隊がのんきに悪魔人間狩りをし続けているのは不合理ではある。往事の特高といえども証拠もなく被疑者を射殺したりはしなかったろう。とはいえ、デーモンの憑依に関するパニックをもっと描くべきだったろう。デーモン(か、悪魔人間)がただ暴れている。警官や悪魔特捜隊が人間狩りをしている。その二つを並べただけで市井の人々のパニックが描けるとも思わない。脚本の段階できっちりとパニックの広がりを描写するべきである。原作でもそれをナレーションで済ませてしまったが、それは五巻ものとしては最良の選択だったはずだ。映画はナレーションをボブ・サップのテレビニュースに集約してしまった分、表現不足に陥っている。何度も同じ店や駅前を定点観測的に写し出すのはよいが、廃墟のマット合成にしてはスケール感に乏しい。白い天主堂も神との関わりを描いてない「DEVILMAN」の世界観の前にはただの建築物でしかなく、聖なる雰囲気は与えられていない。パニック描写の代わりに「ススムくん、大ショック」のエピソードが象徴的に挿入された。ススムくんとチーコの演技に人類の最後の希望が託されてしまうのだが、ススムくんとチーコは実によくそれに応えた。しかしチーコがデビルマンとして覚醒するシーンは伝統的な少女活劇の域に収まってしまった。殺陣もないが演出もないのが悔やまれる。このCGも合格点とは言えないレベルなので、美しい悪魔人間を一体くらいはきちんと造形してほしかった。
原作における牧村美樹の最期は余りにも残虐で衝撃的である。映画ではさすがにあそこまでの描写はない。PG−12どころか上映禁止になりかねない。スプラッター演出を抑えるのはよいことだと個人的には思う。しかし心情的な描写で映画は明らかに原作に劣ってしまった。牧村家に向かう前後の明の気持ちが原作には痛いほど描かれている。しかし映画では明がのそのそしている間に牧村一家が惨殺されて、廃墟となった屋敷で明が美樹の死体と対面するだけだ。原作では暴徒に蹂躙される美樹の肉体を明は目の当たりにする。(読者は生涯消えぬトラウマを植え付けられる。)明の怒りは一瞬にして暴徒を業火で焼き尽くす。美樹を失った明は守るべきものを全て失う。守るべきものとは人類であり、牧村美樹のことだ。明の怒りは読者の怒りであり、明の悲しみは読者の悲しみであり、明の絶望は読者の絶望でもある。原作の読者は牧村美樹を殺戮するような人類に愛想を尽かし、すべての希望を明と同じく失ってしまう。希望のない戦いに勝利はない。こんな人類ならば滅びるしかないと読者は従容せずにはいられない。ストーリーテーラーとしての永井豪の巧みさは正に神懸かりというか、鬼が憑いたと言うべきか。圧倒的な筆圧で読者に迫ってくる。但し、それには牧村美樹が守るべき人類の象徴たり得ているかが重要な大前提となる。酒井彩名は奮闘しているが、果たして観客にそこまでの支持を得ることに成功していたか。役者陣が総崩れの状態では、彼女一人がいくら抗って見せたところで、この作品の「滅亡」を止められるものではない。美樹の死後「DEVILMAN」はその貧相な芝居とプレステ2レベルのCGを駆使し、一気にハルマゲドンを描いてみせる。サタンとデビルマンの一騎打ちによって、それは象徴的に描かれる。デビルマンの足場となるのは無数の裸の人間たちが蠢いている「人類の塔」だ。つまり、デビルマンは人類の命運を背負って、サタンと対決していると説明したいのかもしれないが、読みとれない。前述の「バベルの塔」との関連も見えない。説明は表現ではないが、説明できない表現は一人よがりに過ぎない。
映画には二種類ある。面白い映画と面白くない映画だ。
「DEVILMAN」は面白くない映画である。
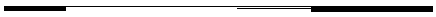
Copyright(C) 1980-2023 SUPER RANDOM Com. All rights reserved